塾長 ブログ
単純でジャンクなものを食べるかどうか
2025/9/3
〇〇人ファーストを掲げる人達がいる。アメリカにもいるし、イギリスにもいる。だから日本にいても不思議ではない。ポリティカル・コレクトネスなど聞こえの良い話は偽物で、粗雑で単純でジャンクに思われる主張こそ本物であるという立脚点は未だ一定支持されているようだ。
多面的に物事を監察し考えることに疲れた人々のニーズに合っているのだろう。しかし、時間をかけた観察や思考にこそ、善なるものがひそんでいると教えてくれる人もいる。
善なるものというのは多くの場合、理解したり嚙み砕いたりするのに時間がかかるし、面倒で退屈な場合が多いんです。でも、「悪しき物語」というのはおおむね単純化されているし、人の心の表面的な層に直接的に訴えかけてきます。ロジックがはしょられているから、話が早くて、受け入れやすい。だから、汚い言葉を使ったヘイトスピーチのほうが、筋の通った立派なスピーチより素早く耳に入ってきます。
(村上春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ』126頁)
多面的に物事を監察し考えることに疲れた人々のニーズに合っているのだろう。しかし、時間をかけた観察や思考にこそ、善なるものがひそんでいると教えてくれる人もいる。
善なるものというのは多くの場合、理解したり嚙み砕いたりするのに時間がかかるし、面倒で退屈な場合が多いんです。でも、「悪しき物語」というのはおおむね単純化されているし、人の心の表面的な層に直接的に訴えかけてきます。ロジックがはしょられているから、話が早くて、受け入れやすい。だから、汚い言葉を使ったヘイトスピーチのほうが、筋の通った立派なスピーチより素早く耳に入ってきます。
(村上春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ』126頁)
学力を測る英語問題-3
2025/8/31
英検3級の過去問から、
問.( )に入れるのに最も適切なものを一つえらびなさい。
Father: Lucy, don't run across the street. ( )
Daughter: Don't worry, Dad. I won't.
1 It's dangerous.
2 It's time to go.
3 It's for you.
4 It's over there.
「ルーシー、通りを走って渡っちゃいけないよ。( )」
「大丈夫よ、お父さん。I won't.」
I won't.をI want.と取り間違える人は2を選ぶ可能性もあります。won't=will notから、それ以下に省略されている個所(重複部分)が何であるかつかむとI won't (run across the street).であることがわかります。
損得が行動基準の人は3を選んでしまうかもしれないし、あっちの横断歩道を渡るように言ってるんだなと勝手に捉えてしまう夢想家は4を選ぶかもしれません。「ダメだ。(理由提示)→反応。情報追加による意思伝達」から、間違いなく1を選べるのが学力のある子です。
問.( )に入れるのに最も適切なものを一つえらびなさい。
Father: Lucy, don't run across the street. ( )
Daughter: Don't worry, Dad. I won't.
1 It's dangerous.
2 It's time to go.
3 It's for you.
4 It's over there.
「ルーシー、通りを走って渡っちゃいけないよ。( )」
「大丈夫よ、お父さん。I won't.」
I won't.をI want.と取り間違える人は2を選ぶ可能性もあります。won't=will notから、それ以下に省略されている個所(重複部分)が何であるかつかむとI won't (run across the street).であることがわかります。
損得が行動基準の人は3を選んでしまうかもしれないし、あっちの横断歩道を渡るように言ってるんだなと勝手に捉えてしまう夢想家は4を選ぶかもしれません。「ダメだ。(理由提示)→反応。情報追加による意思伝達」から、間違いなく1を選べるのが学力のある子です。
#withyou~きみとともに~
2025/8/27
多くの学校で2学期が始まった。タイトルは朝日新聞の子供たちに寄り添う企画から。今回は芥川賞作家の金原ひとみさんだ。小・中学校はほぼ不登校で、高校は数ヶ月で退学したのだそう。
当時は学校の空気と、その中にある全てがいやでした。固定的な人間関係、同じ時間に同じ場所に通うルーティン…。周りの子ともあまり話が合いませんでした。誰かが誰かを好きとか、下ネタとか、子供っぽいと小馬鹿にしているところがありました。〈中略〉
さらに、子ども時代を思い出し、周囲を見下すことで自分を保っていたんだということにも気づけました。
ただ、こうして他人を受け入れられるようになったのは、これまで自分をかたくなに守ってきたからでもあるんです。子どもの時に適応を強制されていたら、精神が持たなかったと思います。
5年くらい前、父に「子どものころが一番つらかった」と話したら、「子どもが苦手な子どもっているんだよ」と言われました。・・・(2025.08.26)
子供の生きづらさが言われる現代。子どもの大変さは「自分が必要としている語彙を、まだ身につけられていない」ことにもあるのではないか。子供と大人で、物事を受信するセンサーの優劣はおそらくない。ものすごく鋭敏にさまざまなものを受け止めるが、語彙が不足しているため、それが何であるかが漠として、自分と周囲の世界との関係性を掴めない。ただ、語彙の獲得にはその語彙が求めるだけの知的な発達が必要で、それにはどうしても時間がかかる。だから、必要なだけの語彙を身につけるまで子供の大変さは続くし、子どもっぽい大人の存在も容易にはなくならない。
当時は学校の空気と、その中にある全てがいやでした。固定的な人間関係、同じ時間に同じ場所に通うルーティン…。周りの子ともあまり話が合いませんでした。誰かが誰かを好きとか、下ネタとか、子供っぽいと小馬鹿にしているところがありました。〈中略〉
さらに、子ども時代を思い出し、周囲を見下すことで自分を保っていたんだということにも気づけました。
ただ、こうして他人を受け入れられるようになったのは、これまで自分をかたくなに守ってきたからでもあるんです。子どもの時に適応を強制されていたら、精神が持たなかったと思います。
5年くらい前、父に「子どものころが一番つらかった」と話したら、「子どもが苦手な子どもっているんだよ」と言われました。・・・(2025.08.26)
子供の生きづらさが言われる現代。子どもの大変さは「自分が必要としている語彙を、まだ身につけられていない」ことにもあるのではないか。子供と大人で、物事を受信するセンサーの優劣はおそらくない。ものすごく鋭敏にさまざまなものを受け止めるが、語彙が不足しているため、それが何であるかが漠として、自分と周囲の世界との関係性を掴めない。ただ、語彙の獲得にはその語彙が求めるだけの知的な発達が必要で、それにはどうしても時間がかかる。だから、必要なだけの語彙を身につけるまで子供の大変さは続くし、子どもっぽい大人の存在も容易にはなくならない。
学力を測る英語問題-2
2025/8/24
英検3級の過去問から、
問.( )に入れるのに最も適切なものを一つえらびなさい。
Son: It's getting dark. ( )
Mother: Yes, please. And close the curtains, too.
1 Can we go home soon?
2 Are you watching TV?
3 Shall I turn on the light?
4 Would you like some breakfast?
「暗くなってきたよ。( )」
「ええ、お願いね。カーテンも閉めてね」の対話が成立するためには、空所内は、「暗くなってきた」に関連する表現で、感謝された上、カーテン「も」閉めてねに続き「得る」ような表現でなければなりません。1ではなく、きちんと3が選べること。そのどこが学力なのって?
その判断力って、立派な学力じゃないですか。
問.( )に入れるのに最も適切なものを一つえらびなさい。
Son: It's getting dark. ( )
Mother: Yes, please. And close the curtains, too.
1 Can we go home soon?
2 Are you watching TV?
3 Shall I turn on the light?
4 Would you like some breakfast?
「暗くなってきたよ。( )」
「ええ、お願いね。カーテンも閉めてね」の対話が成立するためには、空所内は、「暗くなってきた」に関連する表現で、感謝された上、カーテン「も」閉めてねに続き「得る」ような表現でなければなりません。1ではなく、きちんと3が選べること。そのどこが学力なのって?
その判断力って、立派な学力じゃないですか。
〇〇な人に、いいことが起こる
2025/8/19
伊集院静が語ったことば
「仕事の喜びとは何か?結果を称えられることか。金を得ることか?そんなちっぽけなもんじゃない。それは仕事をしていて、自分以外の誰かの役に立っていることがわかることだ。それこそが仕事の真の価値なのだ」
「ジーニアス英和辞典」にこのような例文があった。
―those:those who「(~する)人たち」
Good things happen to those who work hard for other people.
注1)good things複数形=「いくつもいいことが」
注2)動作動詞の現在形=習慣「~するものだ」
「仕事の喜びとは何か?結果を称えられることか。金を得ることか?そんなちっぽけなもんじゃない。それは仕事をしていて、自分以外の誰かの役に立っていることがわかることだ。それこそが仕事の真の価値なのだ」
「ジーニアス英和辞典」にこのような例文があった。
―those:those who「(~する)人たち」
Good things happen to those who work hard for other people.
注1)good things複数形=「いくつもいいことが」
注2)動作動詞の現在形=習慣「~するものだ」

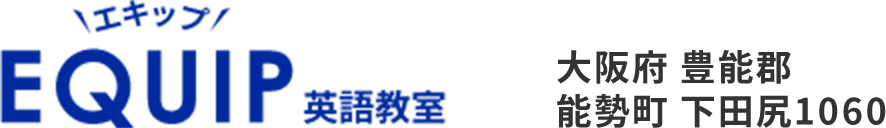


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
