塾長 ブログ
Physical Distancing
2025/2/16
トランプ大統領が第2次政権をスタートさせて一か月。就任直後にいくつもの大統領令に署名しましたが、その中にWHOからの脱退がありました。「新型コロナウイルスのパンデミックへの対応を誤った」ことや「加盟国による不適切な政治的影響からの独立性を示せていない」ことをその理由に挙げています。
コロナ禍の最中、ソーシャルディスタンスという言葉が日本に定着しました。この言葉、実はSkiing→「スキー」と同様に、日本人が得意の簡略表現です。Social Distance「社会的距離」は、本来「心理的なものを含む人と人の距離感」のことなので、Social Distancingとして初めて「感染予防のために対人距離をとる」という意味になります。
しかしながら、socialが持つ「社会的な」というもともとの意味が完全に消えるわけではないので、例えば、家族で食事する際、互いの距離を配慮すると「家族間で社会的距離をとる」ような違和感がどうしても生まれてしまいました。
そこでWHO(世界保健機関)は、より正確に「Physical Distancing」=「物理的距離をとること」という言い方に改めましたが、この表現は日本では定着しませんでした。WHOのコメントを紹介しておきます。
『我々があえてフィジカル・ディスタンシングと言い換えているのは、人と人とのつながりは引き続き保ってほしいと思うからです』
WHOはトランプ大統領との適切な距離を維持できるでしょうか。
コロナ禍の最中、ソーシャルディスタンスという言葉が日本に定着しました。この言葉、実はSkiing→「スキー」と同様に、日本人が得意の簡略表現です。Social Distance「社会的距離」は、本来「心理的なものを含む人と人の距離感」のことなので、Social Distancingとして初めて「感染予防のために対人距離をとる」という意味になります。
しかしながら、socialが持つ「社会的な」というもともとの意味が完全に消えるわけではないので、例えば、家族で食事する際、互いの距離を配慮すると「家族間で社会的距離をとる」ような違和感がどうしても生まれてしまいました。
そこでWHO(世界保健機関)は、より正確に「Physical Distancing」=「物理的距離をとること」という言い方に改めましたが、この表現は日本では定着しませんでした。WHOのコメントを紹介しておきます。
『我々があえてフィジカル・ディスタンシングと言い換えているのは、人と人とのつながりは引き続き保ってほしいと思うからです』
WHOはトランプ大統領との適切な距離を維持できるでしょうか。
外国語学部・国際学部の人気が復活
2025/2/12
関関同立をはじめとする私大入試がひと段落。グローバル、国際関係など外国語を学ぶ学部への志願者が増えているようだ。これらの学部では、コロナ禍で留学が難しかったり、卒業後の就職先が見通せなかったりで志願者が減っていた。新型コロナウイルス感染症も感染症法5類に移行して1年半。ようやく受験生も将来への見通しを持って、「外国語」を学びたいという希望の通りの出願が叶うようになったということだろう。
AIの進化で、外国語学習はもはや必要ではないという人もいるが、自分で外国語を「読んで、聞いて、書いて、話せる」という喜びをAIが与えてくれることはない。外国語を学ぶ道程で、自国言語に対する認識も深まり、世の中の事象にも広く関心を持てるようになるだろう。
外国語を学ぶ際に必要なのは、「コンスタントに継続する力」だろう。そしてこの力が、外国語学習を離れても、さまざまな学びに適応できるものだからこそ、外国語を学習して一定の力をつけた者が評価されるのだろうと考える。
英語と言わず、自分の学びたい外国語学習を継続する人に幸あれ。
AIの進化で、外国語学習はもはや必要ではないという人もいるが、自分で外国語を「読んで、聞いて、書いて、話せる」という喜びをAIが与えてくれることはない。外国語を学ぶ道程で、自国言語に対する認識も深まり、世の中の事象にも広く関心を持てるようになるだろう。
外国語を学ぶ際に必要なのは、「コンスタントに継続する力」だろう。そしてこの力が、外国語学習を離れても、さまざまな学びに適応できるものだからこそ、外国語を学習して一定の力をつけた者が評価されるのだろうと考える。
英語と言わず、自分の学びたい外国語学習を継続する人に幸あれ。
worthは前置詞
2025/2/9
中学校で学習する前置詞は、on / in / at / of / for / about / from / to / with / without / before / after / until[till] / by / between / among / like / as くらいだろうか。
前置詞は名詞の「前に置くもの」だから、
That cloud looks like a rabbit.
「あの雲はウサギのように見える」のような例文で学習すれば、likeが「…が好きだ」の意味の動詞ではないことと共に、別の用法・意味があることを知ることができるだろう。前置詞は「名詞の前に置くもの」だから、名詞としての機能を持つ動名詞(V)ingの前に置くこともできる。
Thank you for inviting us.
「お招きありがとうございます」などは高校入試にはよく出題される。
さて、標記worthだが、高校で使用する文法書の前置詞の項目には出て来ないし、さらに詳しい「ロイヤル英文法」にも前置詞としては取り上げられていない。高2くらいで、
The book is worth reading.
「その本は読む価値がある」などのように出て来ると、The book is good for understanding the universe.などから類推してworthは「価値がある」の意味の形容詞と考えても無理はないだろう。でも、なぜ直後に(V)ingが後続するのかまでは説明できない。be worth (V)ingで「~する価値がある」と記憶するしかない。
でも、「worthは前置詞。だから後ろに動名詞が続くのだ」と理解すれば、納得の度合いも増すかもしれない。
前置詞は名詞の「前に置くもの」だから、
That cloud looks like a rabbit.
「あの雲はウサギのように見える」のような例文で学習すれば、likeが「…が好きだ」の意味の動詞ではないことと共に、別の用法・意味があることを知ることができるだろう。前置詞は「名詞の前に置くもの」だから、名詞としての機能を持つ動名詞(V)ingの前に置くこともできる。
Thank you for inviting us.
「お招きありがとうございます」などは高校入試にはよく出題される。
さて、標記worthだが、高校で使用する文法書の前置詞の項目には出て来ないし、さらに詳しい「ロイヤル英文法」にも前置詞としては取り上げられていない。高2くらいで、
The book is worth reading.
「その本は読む価値がある」などのように出て来ると、The book is good for understanding the universe.などから類推してworthは「価値がある」の意味の形容詞と考えても無理はないだろう。でも、なぜ直後に(V)ingが後続するのかまでは説明できない。be worth (V)ingで「~する価値がある」と記憶するしかない。
でも、「worthは前置詞。だから後ろに動名詞が続くのだ」と理解すれば、納得の度合いも増すかもしれない。
高3の0学期
2025/2/5
共通テストが終わって、個別試験の出願も今日2/5で終了する。比較的高得点の受験生が多かったようで、今年の高3は志望校を変えずに「初志貫徹」の強気出願がトレンドであるらしい。志望校に合格できるよう、出来ることは全てやって個別試験に備えてほしい。
さて、現高2は新高3とも表現されて塾や予備校の春期講習への誘いも始まっているようだ。高2の3学期が「高3の0学期」と呼ばれ始めて久しい。4月から受験勉強を始めるのに比して、1月から開始すれば3カ月のアドバンテージを持つことができる。有効に活用すれば地力を形成することもできる。受験生自身がその時期その時期にやるべきことを計画することはとても難しいから、「良質な受験指導の経験がある人」が「対象者を良く見て、計画を立ててくれる」ような塾や予備校を選びたい。
R7年共通テスト〈英語・リーディング〉の出題語彙を、定番の『シスタン』で調べると、中学学習語彙を除く340語のうち「Stage 1」「Stage 2」「Stage 5」から80%が出題されていた。早期に受験勉強をスタートさせても、基礎を徹底するのが何よりも大切だ。
さて、現高2は新高3とも表現されて塾や予備校の春期講習への誘いも始まっているようだ。高2の3学期が「高3の0学期」と呼ばれ始めて久しい。4月から受験勉強を始めるのに比して、1月から開始すれば3カ月のアドバンテージを持つことができる。有効に活用すれば地力を形成することもできる。受験生自身がその時期その時期にやるべきことを計画することはとても難しいから、「良質な受験指導の経験がある人」が「対象者を良く見て、計画を立ててくれる」ような塾や予備校を選びたい。
R7年共通テスト〈英語・リーディング〉の出題語彙を、定番の『シスタン』で調べると、中学学習語彙を除く340語のうち「Stage 1」「Stage 2」「Stage 5」から80%が出題されていた。早期に受験勉強をスタートさせても、基礎を徹底するのが何よりも大切だ。
go and (V)での、andの脱落
2025/2/2
よく使われる表現には「脱落」が生じることが多いのが言語の特性。
(1) Go to talk to him right away.
to (V)は「~するために」と目的の意の不定詞と理解してもいいですが、toを〈→〉の記号とみなせば、
(1)' Go → talk to him right away.
「行って、話しなさい、彼に、すぐ」と理解しても同じです。
これは次のように表現しても同意です。
(2) Go and talk to him right away.
このような〈go and (V)〉では、しばしばandが脱落し、
(2)' Go talk to him right away.のように「一般動詞が2つ並ぶ」という学校では学習しない表現が出来上がります。でも、英検Listeningなどには頻出するので、「脱落」について一定の知識を持ちたいですね。
「よく使う表現には脱落が生じることが多い」のです。
Go jump in the water.「早く飛び込め」
Go buy 2 French fries.「フライドポテト2つね」
(1) Go to talk to him right away.
to (V)は「~するために」と目的の意の不定詞と理解してもいいですが、toを〈→〉の記号とみなせば、
(1)' Go → talk to him right away.
「行って、話しなさい、彼に、すぐ」と理解しても同じです。
これは次のように表現しても同意です。
(2) Go and talk to him right away.
このような〈go and (V)〉では、しばしばandが脱落し、
(2)' Go talk to him right away.のように「一般動詞が2つ並ぶ」という学校では学習しない表現が出来上がります。でも、英検Listeningなどには頻出するので、「脱落」について一定の知識を持ちたいですね。
「よく使う表現には脱落が生じることが多い」のです。
Go jump in the water.「早く飛び込め」
Go buy 2 French fries.「フライドポテト2つね」

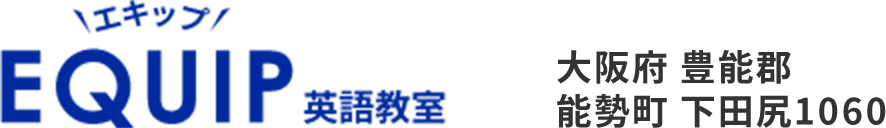


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
