塾長 ブログ
「…は~にある」はThere is[are]…でいいの?
2025/4/27
「…がある」と聞けば、自動的にThere is[are]…構文を思い出す人が多いでしょう。
ただし、There is[are]…の後には〈新情報…話して・聞き手にとって未知の情報である:a+名詞・名詞s〉が続き、〈旧情報…話して・聞き手にとって既知の情報である:the[所有格]+名詞」・「固有名詞〉は続きません。
〇There is a cat on the floor.
×There is the shop on the third floor of this building.
〈旧情報〉「その店は~にある」としたい場合には次のように表現します。
〇The shop is on the third floor of the building.
ここでは、be動詞は「存在する」の意味で、「その店は+存在する+場所を表す副詞句」となります。
〈to be continued〉
ただし、There is[are]…の後には〈新情報…話して・聞き手にとって未知の情報である:a+名詞・名詞s〉が続き、〈旧情報…話して・聞き手にとって既知の情報である:the[所有格]+名詞」・「固有名詞〉は続きません。
〇There is a cat on the floor.
×There is the shop on the third floor of this building.
〈旧情報〉「その店は~にある」としたい場合には次のように表現します。
〇The shop is on the third floor of the building.
ここでは、be動詞は「存在する」の意味で、「その店は+存在する+場所を表す副詞句」となります。
〈to be continued〉
VOICEとは
2025/4/23
語彙力は英語力。覚えている単語数は多ければ多いほど有効です。
語彙はvocabularyと綴りますが、voc-はラテン語で「言葉」を意味するvocabulumを語源とし、さらにこの語は「呼ぶ」を意味するラテン語vocareの派生語です。
voiceやvocalが同語源の語として挙げられます。
「ロングマン]では、voiceをthe sounds that you make when you speakと定義していますが、他にthe right or ability to
express an opinion「発言権」、an opinion or wish that is expressed「意見」を掲載し、「音」が「心や思考の運動を伝える振動」であることを伝えています。
voiceはactive voice・passive voiceというふうにも用いられ、物事を「動作主」から語るのか(能動態)、「対象」から語るのか(受動態)という文構成の関係性を示しもします。
声帯が震える[vo]の音が、単なる音を超えて、周囲に空気に特有の振動を伝え、その振動はそれを聞く人の心も揺らすようです。
語彙はvocabularyと綴りますが、voc-はラテン語で「言葉」を意味するvocabulumを語源とし、さらにこの語は「呼ぶ」を意味するラテン語vocareの派生語です。
voiceやvocalが同語源の語として挙げられます。
「ロングマン]では、voiceをthe sounds that you make when you speakと定義していますが、他にthe right or ability to
express an opinion「発言権」、an opinion or wish that is expressed「意見」を掲載し、「音」が「心や思考の運動を伝える振動」であることを伝えています。
voiceはactive voice・passive voiceというふうにも用いられ、物事を「動作主」から語るのか(能動態)、「対象」から語るのか(受動態)という文構成の関係性を示しもします。
声帯が震える[vo]の音が、単なる音を超えて、周囲に空気に特有の振動を伝え、その振動はそれを聞く人の心も揺らすようです。
英検ライティングの字数制限
2025/4/20
英検協会は、ライティング(英文要約)が課される英検1級~英検準2級プラスの問題指示文の変更を公示しました。
具体的には、
〈変更前[2級]〉
●以下の英文を読んで、その内容を英語で要約し、解答欄に記入しなさい。
●語数の目安は45語から55語です。
〈変更後[2級]〉
●以下の英文を読んで、その内容を45語から55語の英語で要約し、解答欄に記入しなさい。
変更点は、〈目安:45語~55語〉→〈45語~55語で〉と字数の枠組みを守ることが「遵守基準」として明示された点です。
英検の採点基準フレームの中では、この語数指定は重要な位置づけになっていると推量されます。ただの「基準」ではなく、『(厳守すべき)絶対基準』くらいに捉えておく方が賢明です。具体的には、「字数超過や字数不足」の場合、2~3箇所の文法的な間違いによる減点よりも、減点程度はおそらく大きいと思われます。
一方、ライティング(英作文:意見論述)では、「語数の目安は80語~100語」との表記が維持されるようですが、こちらの場合も、「絶対にこの枠内の字数で書かないといけない」と考えるべきです。英検協会は採点基準を明らかにしていませんが、結果は、CSEスコアに明確に反映されます。
具体的には、
〈変更前[2級]〉
●以下の英文を読んで、その内容を英語で要約し、解答欄に記入しなさい。
●語数の目安は45語から55語です。
〈変更後[2級]〉
●以下の英文を読んで、その内容を45語から55語の英語で要約し、解答欄に記入しなさい。
変更点は、〈目安:45語~55語〉→〈45語~55語で〉と字数の枠組みを守ることが「遵守基準」として明示された点です。
英検の採点基準フレームの中では、この語数指定は重要な位置づけになっていると推量されます。ただの「基準」ではなく、『(厳守すべき)絶対基準』くらいに捉えておく方が賢明です。具体的には、「字数超過や字数不足」の場合、2~3箇所の文法的な間違いによる減点よりも、減点程度はおそらく大きいと思われます。
一方、ライティング(英作文:意見論述)では、「語数の目安は80語~100語」との表記が維持されるようですが、こちらの場合も、「絶対にこの枠内の字数で書かないといけない」と考えるべきです。英検協会は採点基準を明らかにしていませんが、結果は、CSEスコアに明確に反映されます。
英検3級~5級で問われる文法事項
2025/4/16
英検取得に必要な要素はいくつもありますが、今回は英検3級~5級で問われる文法事項をまとめておきます。
英検5級
be動詞・現在形[am/are/is]、一般動詞・現在形、現在進行形、疑問詞[Whose, Where, When, What, Which, How]を使った疑問文とその答え方、頻度を表す副詞、Which+名詞・What+名詞・How+形容詞、助動詞can
英検4級
〈英検5級学習事項に加え〉be動詞・一般動詞の過去形、過去進行形、未来[be going to/will]、助動詞[can., could, may, must, have to]、不定詞[名詞・形容詞・副詞の各用法]、動名詞、原級比較・比較級・最上級、There is[are]構文、SVOO文型、接続詞[等位接続詞+,so, because, before, after, if]
英検3級
〈英検5級・4級学習事項に加え〉現在完了、受動態、分詞の形容詞的用法、関係代名詞、間接疑問文・付加疑問文
英語の学習は、既出の学習事項が何度も出て来る「積み上げ型」の構成になります。「あれ~、これ何だっけ?」と思った時にちゃんと振り返って復習・補充することが大切です。「わからない」を放置しない!
英検5級
be動詞・現在形[am/are/is]、一般動詞・現在形、現在進行形、疑問詞[Whose, Where, When, What, Which, How]を使った疑問文とその答え方、頻度を表す副詞、Which+名詞・What+名詞・How+形容詞、助動詞can
英検4級
〈英検5級学習事項に加え〉be動詞・一般動詞の過去形、過去進行形、未来[be going to/will]、助動詞[can., could, may, must, have to]、不定詞[名詞・形容詞・副詞の各用法]、動名詞、原級比較・比較級・最上級、There is[are]構文、SVOO文型、接続詞[等位接続詞+,so, because, before, after, if]
英検3級
〈英検5級・4級学習事項に加え〉現在完了、受動態、分詞の形容詞的用法、関係代名詞、間接疑問文・付加疑問文
英語の学習は、既出の学習事項が何度も出て来る「積み上げ型」の構成になります。「あれ~、これ何だっけ?」と思った時にちゃんと振り返って復習・補充することが大切です。「わからない」を放置しない!
あなたと私のケミストリー
2025/4/13
chemistryとは一般に「化学」のことを表します。
[ロングマン]では、
the science that is conecerned with studying the structure of substances and the way that they change or combine with each otherと定義し、「物質の構造を研究したり、物質が変化あるいは互いに結びつく方法を研究することに係る科学」を意味します。
また、もう一つの定義として、if there is chemistry between two people, they like each other and find each other attractiveを例示し、「もし二者間にケミストリーがあれば、互いに好意を持ち、魅力的な存在だと気づくことになる」という状況を挙げています。
そう、chemistryには「相性」という、「人間-人間」という要素の結びつき方やその反応・作用を意味する場合もあるのです。
ケミストリーの合う人、大切にしたいですね。
[ロングマン]では、
the science that is conecerned with studying the structure of substances and the way that they change or combine with each otherと定義し、「物質の構造を研究したり、物質が変化あるいは互いに結びつく方法を研究することに係る科学」を意味します。
また、もう一つの定義として、if there is chemistry between two people, they like each other and find each other attractiveを例示し、「もし二者間にケミストリーがあれば、互いに好意を持ち、魅力的な存在だと気づくことになる」という状況を挙げています。
そう、chemistryには「相性」という、「人間-人間」という要素の結びつき方やその反応・作用を意味する場合もあるのです。
ケミストリーの合う人、大切にしたいですね。

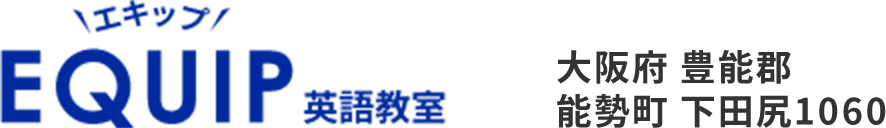


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
