塾長 ブログ
a computer / computers
2025/7/30
「私はネコが好きです」なら、I like cats.とcatを複数形で表します。ネコは同時に複数いて、それで自然だからです。数えられる名詞の単数・複数は悩ましい問題ですが、予め「この単語は単数でとか、この単語は複数で」と決まっているものではなくて、場面に応じて自然な方を選ぶという発想が大切です。
「コンピュータは日々の生活に欠かせないものになっている」と表現したければ、どのコンピュータと限定するものではなく、世の中にあまねく存在するコンピュータという意味ですから、
Computers have become an integral part of our daily lives.
となるのが自然ですし、
「コンピュータを使う時には2時間に1回は休憩した方がよい」であれば、目の前にあるコンピュータは通常1台でしょうから、
When using a computer, it is better to take a break every two hours.
が自然な表現になります。
「コンピュータは日々の生活に欠かせないものになっている」と表現したければ、どのコンピュータと限定するものではなく、世の中にあまねく存在するコンピュータという意味ですから、
Computers have become an integral part of our daily lives.
となるのが自然ですし、
「コンピュータを使う時には2時間に1回は休憩した方がよい」であれば、目の前にあるコンピュータは通常1台でしょうから、
When using a computer, it is better to take a break every two hours.
が自然な表現になります。
声を低くすると
2025/7/27
7/2の塾長ブログに書いた。説得的話法のためには、アリストテレス『弁論術』によれば、Logic(話の論理)とEthics(話者の倫理)、さらにPassion(伝えようとする熱情)が必要だと。加えて、相手により信頼感を持ってもらうにはVoiceの質も重要だ。
自分の主張を相手に届けることを仕事の基礎とする政治家は、世界的に見れば声が低い。もう亡くなられたが米国の元国務長官:キッシンジャーなどは声がとても低かった。女性は男性よりも声が高いのだが、鉄の女と称された英国のサッチャー元首相は、権威を得るために声の周波数を60ヘルツも下げたそうだ。
一般的に声が高い人は低い人に比べ「真実味や力強さに欠ける」との印象を持たれる傾向があるという。米国の元国務長官:ヒラリー・クリントンやドイツのメルケル元首相も意図的に声を低くしたことが知られる。
日本人女性の声は世界的に見ると高いグループに属すという。話の中身も大事だが、その話を相手に届けるVoiceの質にも意識を持ってはどうだろう。
聞いた話だが、かつてのブロードウェイのミュージカル、その後オードリー・ヘプバーンが主演して映画化された『My Fair Lady』でも、その人が属する社会階級を声の高低が興味深く描いている(らしい)。音声学者のヒギンズ教授が、ロンドン下町のコックニー訛りの花売り娘イライザを舞踏会で通用するレディに仕立て上げる話だ。今年の夏の研究課題として古い映画を楽しもうと思っている。
自分の主張を相手に届けることを仕事の基礎とする政治家は、世界的に見れば声が低い。もう亡くなられたが米国の元国務長官:キッシンジャーなどは声がとても低かった。女性は男性よりも声が高いのだが、鉄の女と称された英国のサッチャー元首相は、権威を得るために声の周波数を60ヘルツも下げたそうだ。
一般的に声が高い人は低い人に比べ「真実味や力強さに欠ける」との印象を持たれる傾向があるという。米国の元国務長官:ヒラリー・クリントンやドイツのメルケル元首相も意図的に声を低くしたことが知られる。
日本人女性の声は世界的に見ると高いグループに属すという。話の中身も大事だが、その話を相手に届けるVoiceの質にも意識を持ってはどうだろう。
聞いた話だが、かつてのブロードウェイのミュージカル、その後オードリー・ヘプバーンが主演して映画化された『My Fair Lady』でも、その人が属する社会階級を声の高低が興味深く描いている(らしい)。音声学者のヒギンズ教授が、ロンドン下町のコックニー訛りの花売り娘イライザを舞踏会で通用するレディに仕立て上げる話だ。今年の夏の研究課題として古い映画を楽しもうと思っている。
prepareの使い方に注意
2025/7/23
「…に備える」の意味で、prepareを使う時には用法に注意する必要があります。
prepareを他動詞として使って、prepare an examとした場合、「試験の準備をする」の意味になりますが、これは「教師が試験問題を作問・印刷して準備をする」の意味であって、生徒が「試験の準備=試験勉強する」という意味にはなりません。生徒が「試験に備えて準備する」の意味でprepareを使うのであれば、prepare for an examとしなければなりません。prepareの後に目的語を置く場合には、その対象である「準備物」を置く必要があるのです。これは「…を手伝う」の意味でhelpを使う場合と同様に、目的語に何を置くべきなのかというセンサーを鋭敏にしなければならない例と言えます。
helpの対象になり得るのは「人」ですから、「宿題」を目的語の位置に置くことはできないのです。この辺りが、日本語ベースで思考して、英語に変換していると間違えてしまうチェックポイントと言えるでしょう。
My father helped me with my homework.
prepareを他動詞として使って、prepare an examとした場合、「試験の準備をする」の意味になりますが、これは「教師が試験問題を作問・印刷して準備をする」の意味であって、生徒が「試験の準備=試験勉強する」という意味にはなりません。生徒が「試験に備えて準備する」の意味でprepareを使うのであれば、prepare for an examとしなければなりません。prepareの後に目的語を置く場合には、その対象である「準備物」を置く必要があるのです。これは「…を手伝う」の意味でhelpを使う場合と同様に、目的語に何を置くべきなのかというセンサーを鋭敏にしなければならない例と言えます。
helpの対象になり得るのは「人」ですから、「宿題」を目的語の位置に置くことはできないのです。この辺りが、日本語ベースで思考して、英語に変換していると間違えてしまうチェックポイントと言えるでしょう。
My father helped me with my homework.
即決がよいとは限らない
2025/7/20
Immediate decision is not always better.
などと書くと、どこかの会社経営者に怒られたり、WOOPの法則論者にバカにされたりしそうだが、即決せずに問題を「先送り」するのが吉と出る場合もある。
これが最適解であると胸を張って力強く述べるのは、今や一つのリーダー像になっているのかもしれないが、「最適解」というのは現状ベースの理解が基になっているから、それが果たして将来、見込んだように機能するかどうかはわからない。エビデンスを根拠に自説をぶつのは勝手だが、未来を完全予測することなど不可能だ。
未来はどうなるかわからないものなのに、現状を最優先し、「未来の未知性」を軽んじる傾向があるのだろう。かつては米国式の「四半期」決算を遠くから眺めていた日本の企業家も、今や「当面の成果をどうマネージして市場関係者に説明するか」に腐心しなければならない時代となっている。
もう少し落ち着いた知性の働かせ方を採用するほうがよさそうだ。「どうしたらよいかわからない時に、なお適切にふるまえること」を知性の定義とするなら、その適切なふるまいの中に「しばし保留」を組み込むことも許されるだろう。
などと書くと、どこかの会社経営者に怒られたり、WOOPの法則論者にバカにされたりしそうだが、即決せずに問題を「先送り」するのが吉と出る場合もある。
これが最適解であると胸を張って力強く述べるのは、今や一つのリーダー像になっているのかもしれないが、「最適解」というのは現状ベースの理解が基になっているから、それが果たして将来、見込んだように機能するかどうかはわからない。エビデンスを根拠に自説をぶつのは勝手だが、未来を完全予測することなど不可能だ。
未来はどうなるかわからないものなのに、現状を最優先し、「未来の未知性」を軽んじる傾向があるのだろう。かつては米国式の「四半期」決算を遠くから眺めていた日本の企業家も、今や「当面の成果をどうマネージして市場関係者に説明するか」に腐心しなければならない時代となっている。
もう少し落ち着いた知性の働かせ方を採用するほうがよさそうだ。「どうしたらよいかわからない時に、なお適切にふるまえること」を知性の定義とするなら、その適切なふるまいの中に「しばし保留」を組み込むことも許されるだろう。
(V)ingは「過去・現在」、to (V)は「未来」
2025/7/16
接続詞を用いない一つの文で、2つの動詞を使うのはルール違反というのが英語だから、(V)ing / to (V)を用いて、
×I like play soccer.
〇I like playing soccer. / I like to play soccer.
と表現することになる。
だが、(V)ingは「過去方向」を表すのに対して、to (V)は「未来方向」を表す表現だから、rememberなどは、
I remember seeing him at the party.
「パーティーで彼に会ったのを覚えている」
Remember to turn off the light.
「電気を消すのを覚えていてね」
のように使い分けなければならない。
上記のlikeにしても、明らかに「未来」を表す場合には、「過去方向」の(V)ingを用いることは出来ず、
I would like to live in Hawaii.
としなければならない。
「動作動詞の現在形は習慣を表す」から、「ワインを2本も空けてから車を運転するのは危険だ」は、
×It would be dangerous that you drive a car after drinking two bottles of wine.
とは表現できず、
〇It would be dangerous to drive a car after drinking two bottles of wine.
としなければならないが、「to (V)は未来を表す」が身体化していないと2文の差を感知するのも難しくなってしまう。
(V)ingは「過去方向」を表すのに対して、to (V)は「未来方向」を表すのだということを英語学習の初期に理解させるような手順が必要だ。
×I like play soccer.
〇I like playing soccer. / I like to play soccer.
と表現することになる。
だが、(V)ingは「過去方向」を表すのに対して、to (V)は「未来方向」を表す表現だから、rememberなどは、
I remember seeing him at the party.
「パーティーで彼に会ったのを覚えている」
Remember to turn off the light.
「電気を消すのを覚えていてね」
のように使い分けなければならない。
上記のlikeにしても、明らかに「未来」を表す場合には、「過去方向」の(V)ingを用いることは出来ず、
I would like to live in Hawaii.
としなければならない。
「動作動詞の現在形は習慣を表す」から、「ワインを2本も空けてから車を運転するのは危険だ」は、
×It would be dangerous that you drive a car after drinking two bottles of wine.
とは表現できず、
〇It would be dangerous to drive a car after drinking two bottles of wine.
としなければならないが、「to (V)は未来を表す」が身体化していないと2文の差を感知するのも難しくなってしまう。
(V)ingは「過去方向」を表すのに対して、to (V)は「未来方向」を表すのだということを英語学習の初期に理解させるような手順が必要だ。

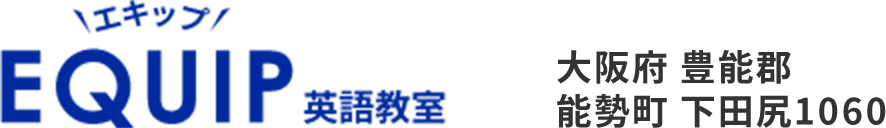


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
