塾長 ブログ
普通の文法書には載っていない
2026/1/18
We have been best friends for five years.
「私たちは5年来の親友だ」
状態動詞を用いて「…の間ずっと~だった」という場合には〈have+状態動詞の過去分詞+for+期間を表す名詞〉の形をとります。この期間を表すforについてはどの参考書・問題集にも説明や練習問題があります。
一方、動作動詞を用いて同様の表現をする場合について触れている参考書・問題集はほぼありません。
This town has changed greatly over [in] the last ten years.
「この10年で、この町は大いに変わった」
のように、期間を表す語はforではなくて、over/inを用いるのです。
このover/inについて解説している参考書や問題集はほぼありませんが、英検の問題ではよくお目にかかる頻出表現です。
注)現在完了進行形〈have+been+(V)ing〉には、期間を表すforを使います。
Our sales have been increasing for the last two years.
「私たちは5年来の親友だ」
状態動詞を用いて「…の間ずっと~だった」という場合には〈have+状態動詞の過去分詞+for+期間を表す名詞〉の形をとります。この期間を表すforについてはどの参考書・問題集にも説明や練習問題があります。
一方、動作動詞を用いて同様の表現をする場合について触れている参考書・問題集はほぼありません。
This town has changed greatly over [in] the last ten years.
「この10年で、この町は大いに変わった」
のように、期間を表す語はforではなくて、over/inを用いるのです。
このover/inについて解説している参考書や問題集はほぼありませんが、英検の問題ではよくお目にかかる頻出表現です。
注)現在完了進行形〈have+been+(V)ing〉には、期間を表すforを使います。
Our sales have been increasing for the last two years.
結局、外国語習得に必要なのは
2026/1/14
AI翻訳機能が発達した現在「外国語を学ぶ必要はもうない」のでしょうか。英語力ゼロから2年でスポーツ通訳者になった酒井 龍さんの勉強法は、
「1冊の英単語帳」を約250周。「同じ教材」を1年間、1,200回のシャドーイング(聞いた音声の後をすぐに追いかけるように復唱する学習法)」だったそうだ。
「反復は大事ですが、もっと大事なのは継続。さらに言うと、やめないこと」が語学学習には大切だと。
駿台予備学校の竹岡広信先生の話では、「同じテキストを5周勉強した生徒は、その学習集団の上位20%に入る学力を身につける」のだそうだ。また東大合格者は「同じテキストを13周は勉強する」らしい。東大に合格する受験生の努力もすごいが、酒井さんの単語集×250周は桁違いだ。1,200回のシャドーイングということは、1日当たり3周以上している。まさに「英語にどっぷり浸かって、飽きもせず『同じテキスト』を繰り返し続けた先に、語学を極めた今の英語力があった」ということだ。
「1冊の英単語帳」を約250周。「同じ教材」を1年間、1,200回のシャドーイング(聞いた音声の後をすぐに追いかけるように復唱する学習法)」だったそうだ。
「反復は大事ですが、もっと大事なのは継続。さらに言うと、やめないこと」が語学学習には大切だと。
駿台予備学校の竹岡広信先生の話では、「同じテキストを5周勉強した生徒は、その学習集団の上位20%に入る学力を身につける」のだそうだ。また東大合格者は「同じテキストを13周は勉強する」らしい。東大に合格する受験生の努力もすごいが、酒井さんの単語集×250周は桁違いだ。1,200回のシャドーイングということは、1日当たり3周以上している。まさに「英語にどっぷり浸かって、飽きもせず『同じテキスト』を繰り返し続けた先に、語学を極めた今の英語力があった」ということだ。
have+(V)p.p.の「アキハバラ」現象とは
2026/1/11
have+(V)p.p.で現在完了を表します。
He has done it. → Has he done it?
となりますから、
He speaks French. → Does he speak French?
のDoesと同様に、have/hasは「助動詞」と理解されます。
他の助動詞との違いはhave/hasの後が動詞の原形ではなく、(V)p,p.の過去分詞形となることです。
現在完了は、昔むかし〈have+名詞+他動詞の過去分詞形〉/〈be動詞+自動詞の過去分詞形〉で表されていました。
〈昔〉I have it done. → 〈今〉I have done it.
このように語が入れ替わる現象は「アキハバラ現象」と呼ばれるそうです。「秋葉原」の本来の読みは「アキバハラ」でしたが、今では「アキハバラ」となっています。でも通称は「アキバ」。
発音のし易さが優先されるのは言語に共通する特徴なのでしょう。
He has done it. → Has he done it?
となりますから、
He speaks French. → Does he speak French?
のDoesと同様に、have/hasは「助動詞」と理解されます。
他の助動詞との違いはhave/hasの後が動詞の原形ではなく、(V)p,p.の過去分詞形となることです。
現在完了は、昔むかし〈have+名詞+他動詞の過去分詞形〉/〈be動詞+自動詞の過去分詞形〉で表されていました。
〈昔〉I have it done. → 〈今〉I have done it.
このように語が入れ替わる現象は「アキハバラ現象」と呼ばれるそうです。「秋葉原」の本来の読みは「アキバハラ」でしたが、今では「アキハバラ」となっています。でも通称は「アキバ」。
発音のし易さが優先されるのは言語に共通する特徴なのでしょう。
中2生・高2生に今必要なことは
2026/1/7
年の初めは多くの学校が3学期。中3や高3になるにはあと3カ月あるこの時期に、ゆっくりでも受験勉強へのスタートを切ることが重要です。中でも重要なのが、始めた学習習慣を「継続する」こと。一番重要で且つ、一番難しいことでもあります。
学習を継続させるために必要なのは「適切な目標設定」ではないでしょうか。スポーツなら〇月〇日に大会があるという予定に合わせて、それに対し「現状課題をどう克服し、目標達成に向かうか」を考えると思います。学習においても、ただ1日2時間英語の勉強をしようでは継続は難しいものになるでしょう。
目標とする高校入試や大学入試に向けた学習と、学習ベクトルの方向性が同じ親和性の高い学習を設定できるかが「学習継続」のモチベーション上重要です。
英語学習でいえば、今の英語力に合わせた英検級取得の学習が、そのまま高校受験や大学受験のための基幹学習となり得ます。
2026年度第1回の英検は5月末に実施されます。これまで英検を受験したことがないならば、今の英語力に合いそうな級と、その一つ上の級のダブル受験を考えて学習計画を作るのもいいでしょう。
目標のあるところに実践への道が拓かれます。
学習を継続させるために必要なのは「適切な目標設定」ではないでしょうか。スポーツなら〇月〇日に大会があるという予定に合わせて、それに対し「現状課題をどう克服し、目標達成に向かうか」を考えると思います。学習においても、ただ1日2時間英語の勉強をしようでは継続は難しいものになるでしょう。
目標とする高校入試や大学入試に向けた学習と、学習ベクトルの方向性が同じ親和性の高い学習を設定できるかが「学習継続」のモチベーション上重要です。
英語学習でいえば、今の英語力に合わせた英検級取得の学習が、そのまま高校受験や大学受験のための基幹学習となり得ます。
2026年度第1回の英検は5月末に実施されます。これまで英検を受験したことがないならば、今の英語力に合いそうな級と、その一つ上の級のダブル受験を考えて学習計画を作るのもいいでしょう。
目標のあるところに実践への道が拓かれます。
「『~した』は過去形で表す」は本当か
2026/1/4
日本語では「~した」と表現するものを、英語で表現しようとする場合には、「それが『現在』とつながりがあるか」を考える必要があります。
I lost the key yesterday.
なら、昨日「鍵を失くした」ことは分かりますが、その鍵が今どうなっているかはこの文からだけでは不明です。
I have lost the key.
と現在完了形で表現すれば、「鍵を失くしたということが、現在もまだ続いている」=「鍵がまだ見つかっていない」という意味になります。
「過去」と「現在」をつなぐ表現が「現在完了形」なのです。
だから、現在完了形と「過去を明示する語」を一緒に使うことはできません。
×I have lost the key yesterday.
I lost the key yesterday.
なら、昨日「鍵を失くした」ことは分かりますが、その鍵が今どうなっているかはこの文からだけでは不明です。
I have lost the key.
と現在完了形で表現すれば、「鍵を失くしたということが、現在もまだ続いている」=「鍵がまだ見つかっていない」という意味になります。
「過去」と「現在」をつなぐ表現が「現在完了形」なのです。
だから、現在完了形と「過去を明示する語」を一緒に使うことはできません。
×I have lost the key yesterday.

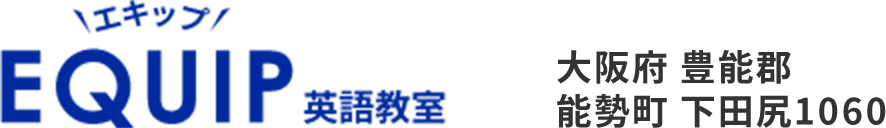


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
