塾長 ブログ
なぜか今、伊集院静「贈る言葉」より
2025/8/17
新社会人おめでとう。
君は今春、どんな職場でどんな仕事に就いただろうか。そこが君の出発点だ。君を迎えた人たちは皆、こころから祝福している。どうして皆がおめでとうというのだろうか。
世の中にはさまざまな事情で働けない人たちが大勢いる。その人たちの夢を私は聞いたことがある。「どんな仕事でもいいから働きたい。働いて一人前の人として生きたい」。皆知っているんだ。仕事をする、働くことがどんなに素晴らしいかということを。
仕事とはきびしいものか?それはきびしいに決まっている。仕事はつらいか?勿論、つらい時もある。耐えなくてはいけない時があるか?ある、ある。でもそんなものは仕事の一部分でしかない。仕事には私たちを辛苦に耐えさせる何かがある。
働くことで人は今の社会を作ってきた。そうでなければとうに人類は地球から消えている。すべての人の生に尊厳があるように、どんな仕事にも尊厳がある。生きる喜びがあるように、仕事にも喜びがあることを、君はいつか知るだろう。
仕事の喜びとは何か?結果を称えられることか。金を得ることか?そんなちっぽけなもんじゃない。それは仕事をしていて、自分以外の誰かの役に立っていることがわかることだ。それこそが仕事の真の価値なのだ。
初仕事をはじめる前に守ってほしいことがある。それは今まで君が生きてきて大切にしていたものを捨てないことだ。
ファッションでも、音楽でも、恋愛だっていいんだ。大切にしているものには、そこに個性がある。個性は君そのものであり、創造の原動力だ。皆が同じカラーで仕事をする時代は終わったんだ。
いつか個性が役立つ時がくる。いつか喜びを知る時がくる。目指す頂は高いぞ。
その時のために身体をこころを鍛えておこう。2008.4.1
君は今春、どんな職場でどんな仕事に就いただろうか。そこが君の出発点だ。君を迎えた人たちは皆、こころから祝福している。どうして皆がおめでとうというのだろうか。
世の中にはさまざまな事情で働けない人たちが大勢いる。その人たちの夢を私は聞いたことがある。「どんな仕事でもいいから働きたい。働いて一人前の人として生きたい」。皆知っているんだ。仕事をする、働くことがどんなに素晴らしいかということを。
仕事とはきびしいものか?それはきびしいに決まっている。仕事はつらいか?勿論、つらい時もある。耐えなくてはいけない時があるか?ある、ある。でもそんなものは仕事の一部分でしかない。仕事には私たちを辛苦に耐えさせる何かがある。
働くことで人は今の社会を作ってきた。そうでなければとうに人類は地球から消えている。すべての人の生に尊厳があるように、どんな仕事にも尊厳がある。生きる喜びがあるように、仕事にも喜びがあることを、君はいつか知るだろう。
仕事の喜びとは何か?結果を称えられることか。金を得ることか?そんなちっぽけなもんじゃない。それは仕事をしていて、自分以外の誰かの役に立っていることがわかることだ。それこそが仕事の真の価値なのだ。
初仕事をはじめる前に守ってほしいことがある。それは今まで君が生きてきて大切にしていたものを捨てないことだ。
ファッションでも、音楽でも、恋愛だっていいんだ。大切にしているものには、そこに個性がある。個性は君そのものであり、創造の原動力だ。皆が同じカラーで仕事をする時代は終わったんだ。
いつか個性が役立つ時がくる。いつか喜びを知る時がくる。目指す頂は高いぞ。
その時のために身体をこころを鍛えておこう。2008.4.1
学力を測る英語問題
2025/8/13
入試や検定試験での英語問題は、もちろん英語力を測るために作られていますが、その英語力を支える「学力」をも測るように準備されています。入試を受けて、ある高校や大学に進学したとして、そこでの学業や研究に立ち向かうには、単に英語力があるかどうかだけではなく、より幅広い未知の「知」にたじろがない、その人の地力が必要とされるのです。それが、高校・大学の先生が生徒に求める「学力」です。
英検3級の過去問から、
問.( )に入れるのに最も適切なものを一つえらびなさい。
A: Thanks for lending me this book.
I really enjoyed it.
B: You can ( ) it if you like.
1 win 2 wait 3 rise 4 keep
英語力を持っていれば、空所に入るのは「助動詞canの後だから動詞の原形」で、「目的語itをとる他動詞であることが分かります。1~4は全て動詞の原形で、通常他動詞として使用されるのは1 win、と4 keep。
もちろん、A「貸してくれてありがとう。この本とてもおもしろかった」に対して、B「よかったら、( )してていいよ」という発言に繋がるのは、keepしかないのだけれど、この「もちろん、keepだよね」と判断を下せるのが、求められている「学力」なのです。
何なに、簡単すぎるって?それはあなたに「学力」が備わっているからですよ。
英検3級の過去問から、
問.( )に入れるのに最も適切なものを一つえらびなさい。
A: Thanks for lending me this book.
I really enjoyed it.
B: You can ( ) it if you like.
1 win 2 wait 3 rise 4 keep
英語力を持っていれば、空所に入るのは「助動詞canの後だから動詞の原形」で、「目的語itをとる他動詞であることが分かります。1~4は全て動詞の原形で、通常他動詞として使用されるのは1 win、と4 keep。
もちろん、A「貸してくれてありがとう。この本とてもおもしろかった」に対して、B「よかったら、( )してていいよ」という発言に繋がるのは、keepしかないのだけれど、この「もちろん、keepだよね」と判断を下せるのが、求められている「学力」なのです。
何なに、簡単すぎるって?それはあなたに「学力」が備わっているからですよ。
an elevator / the elevator
2025/8/10
数えられる名詞につける、aとtheもどう選択すればよいか悩んでしまう場面があるでしょう。
「エレベータが来るのを待つ時に、10秒も経たないうちにイラついてしまう」であれば、
When I wait for an elevator / the elavator to come, I get annoyed within 10 seconds.
でしょうが、an elavatorと表現すべきか、the elevatorとすべきか悩んでしまうのではないでしょうか。
ここでのエレベータは、任意の昇降装置であり、ボタンを押して到着するのは通常1台のエレベータでしょうから、elevatorsよりはan elevatorの方が自然でしょう。また、何か特定のエレベータを指すのではなく、どれかやってくる1台のエレベータですから、the elevatorよりもan elevatorの方が適切であるようにも思われます。しかし、一番自然な表現は、
When I wait for the elavator to come, I get annoyed within 10 seconds.
です。「仮想の場面であっても、やって来るのは目の前にある(限定された)エレベータ」と考えるのです。場面想起力が必要とされますね。
「エレベータが来るのを待つ時に、10秒も経たないうちにイラついてしまう」であれば、
When I wait for an elevator / the elavator to come, I get annoyed within 10 seconds.
でしょうが、an elavatorと表現すべきか、the elevatorとすべきか悩んでしまうのではないでしょうか。
ここでのエレベータは、任意の昇降装置であり、ボタンを押して到着するのは通常1台のエレベータでしょうから、elevatorsよりはan elevatorの方が自然でしょう。また、何か特定のエレベータを指すのではなく、どれかやってくる1台のエレベータですから、the elevatorよりもan elevatorの方が適切であるようにも思われます。しかし、一番自然な表現は、
When I wait for the elavator to come, I get annoyed within 10 seconds.
です。「仮想の場面であっても、やって来るのは目の前にある(限定された)エレベータ」と考えるのです。場面想起力が必要とされますね。
文科省調査~学力・大幅低下
2025/8/6
3年毎にほぼ同じ問題で小6・中3生の学力変化をみる「経年変化分析調査」の結果が発表された。対象教科は小学生が「国・数」で、中学生が「国・数・英」。結果は500を基準とするスコアで示されるが、全教科でスコアが低下した。中でも一番低下したのが中3生の英語で、スコアは478.2(前回比22.9ポイント減)という。
学力調査と同時に行われた周辺調査では、勉強時間が長いほど成績は高く、スマホの使用・ゲーム遊びも時間が長いほど成績スコアは低かった。この辺りは当たり前の結果。つまり、勉強すればするほど学力は高くなるが、やらなければ身につくはずもないということ。
文科省の見解では、中3生は小学校で外国語を習い始めた時期がコロナ禍と重なり「話すこと」が積極的に出来なかった影響と分析しているそうだ。だが、果たしてそうか?
お茶の水女子大学名誉教授の耳塚先生による要因分析では、①勉強時間の減少、②「知識・技能」の定着不足、③家庭の経済的背景、④デジタル環境の影響が考えられるという。
おそらく、最も重要なのは②であろう。「知識・技能」と対置されるのは「思考力・判断力・表現力」だが、前者を軽視し、後者にスタンスする傾向が近年、学校現場では非常に強い。どんどん英語を使うことが文科省の求める方向なのだろうが、空っぽの容器からさまざまな知的表現が泉のごとく湧き出るはずがない。アウトプットのためには、しかるべき量に達するまで必要な知識をインプットする必要がある。「知識・技能の再評価・再構築」がなければ、英語力の低下は止まらないだろう。
学力調査と同時に行われた周辺調査では、勉強時間が長いほど成績は高く、スマホの使用・ゲーム遊びも時間が長いほど成績スコアは低かった。この辺りは当たり前の結果。つまり、勉強すればするほど学力は高くなるが、やらなければ身につくはずもないということ。
文科省の見解では、中3生は小学校で外国語を習い始めた時期がコロナ禍と重なり「話すこと」が積極的に出来なかった影響と分析しているそうだ。だが、果たしてそうか?
お茶の水女子大学名誉教授の耳塚先生による要因分析では、①勉強時間の減少、②「知識・技能」の定着不足、③家庭の経済的背景、④デジタル環境の影響が考えられるという。
おそらく、最も重要なのは②であろう。「知識・技能」と対置されるのは「思考力・判断力・表現力」だが、前者を軽視し、後者にスタンスする傾向が近年、学校現場では非常に強い。どんどん英語を使うことが文科省の求める方向なのだろうが、空っぽの容器からさまざまな知的表現が泉のごとく湧き出るはずがない。アウトプットのためには、しかるべき量に達するまで必要な知識をインプットする必要がある。「知識・技能の再評価・再構築」がなければ、英語力の低下は止まらないだろう。
駿台予備校の決断
2025/8/3
駿台予備学校が2026年度から、各大学・学部の合格者数の公表をおこなわないと発表した。受験生の多くが複数の塾・予備校やオンライン教材等を併用して学ぶことが一般的となり、単一の教育機関における合格者数が本来の意味を持ちにくくなってきているのが理由だという。
例えば、2025年度入試において、東大の一般選抜前期日程の合格者は2,997名だったが、主要な塾・予備校が公表する合格者数を合計すると、実際の定員を大きく上回る数字になり、その数値の信頼性や意味が形骸化しているとの判断だったようだ。
合格者数は塾・予備校にとって、「信頼」や「実績」の象徴であり、受験生や保護者にとって学習機関決定の重要な指標であった。予備校のトップランナーである駿台だからこそ出来る自信の成せる技なのであろうが、これに追従できる塾・予備校はあるだろうか。
また、大学合格実績を多くの高校が公表しているが、自校の教員による指導で合格に導いたと言える高校がどれだけあるだろうか。大学合格数だけでは分からない、各高校の本当の学習指導力を見極める力が、中学校の先生や高校受験塾の指導者に必要だということを思い知らされた大きな決断だった。
例えば、2025年度入試において、東大の一般選抜前期日程の合格者は2,997名だったが、主要な塾・予備校が公表する合格者数を合計すると、実際の定員を大きく上回る数字になり、その数値の信頼性や意味が形骸化しているとの判断だったようだ。
合格者数は塾・予備校にとって、「信頼」や「実績」の象徴であり、受験生や保護者にとって学習機関決定の重要な指標であった。予備校のトップランナーである駿台だからこそ出来る自信の成せる技なのであろうが、これに追従できる塾・予備校はあるだろうか。
また、大学合格実績を多くの高校が公表しているが、自校の教員による指導で合格に導いたと言える高校がどれだけあるだろうか。大学合格数だけでは分からない、各高校の本当の学習指導力を見極める力が、中学校の先生や高校受験塾の指導者に必要だということを思い知らされた大きな決断だった。

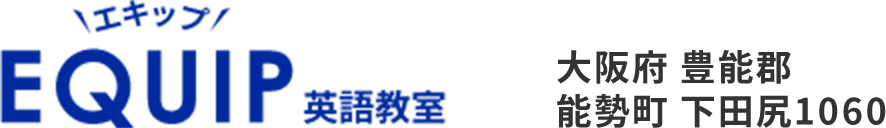


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
