塾長 ブログ
Forever Green
2025/4/9
言葉は文化の象徴ですが、言葉は思考も支配します。
A rolling stone gathers no moss.
「転石苔むさず」ということわざがありますね。苔を良いものとみなすかどうかで意味が変わってきたと言われます。
伝統を重んじる保守的な英国では、苔は時間をかけて形成される歴史や風格を投影するのに対し、自由を尊重する改革的な米国では悪しき習慣や慣例として連想されやすく、文化的背景により正反対の意味に取られています。
文化が違えば、虹は七色とは限らないし、信号の色も青と表現する文化もあれば、緑と表現する文化もあります。
Foreever Greenはどうでしょうか。
「常緑」→「いつまでも新鮮な、若々しい」のポジティブの意も表しますし、「常緑」→「いつまでも青い、青二才」のネガティブ表現ともなり得ます。これは文化による違いではなくて、対象となっている人が他の人にどのように映っているかということによって意味合いが違ってきているのですね。
A rolling stone gathers no moss.
「転石苔むさず」ということわざがありますね。苔を良いものとみなすかどうかで意味が変わってきたと言われます。
伝統を重んじる保守的な英国では、苔は時間をかけて形成される歴史や風格を投影するのに対し、自由を尊重する改革的な米国では悪しき習慣や慣例として連想されやすく、文化的背景により正反対の意味に取られています。
文化が違えば、虹は七色とは限らないし、信号の色も青と表現する文化もあれば、緑と表現する文化もあります。
Foreever Greenはどうでしょうか。
「常緑」→「いつまでも新鮮な、若々しい」のポジティブの意も表しますし、「常緑」→「いつまでも青い、青二才」のネガティブ表現ともなり得ます。これは文化による違いではなくて、対象となっている人が他の人にどのように映っているかということによって意味合いが違ってきているのですね。
becauseの品詞は
2025/4/6
A: Why were you absent from school yesterday?
B: Because I was sick in bed.
中学でbecauseを学ぶ基本的フレーズです。
Why~?に対して、Because~.で理由を述べるのだなということが刷り込まれます。ただ、Becauseは理由を述べる枕詞のようなものだとの理解が主で、品詞について意識が及ぶことはまれでしょう。
しかしやがて、次のような文に出会って、
We stopped playing tennis because it bagan to rain.
「We stopped playing tennis」「+ because←it began to rain.」
becauseは「理由を表す」と共に、前後の「文を結びつける」働きがあるのだと理解します。つまり、ifやwhenと同じ「接続詞」なんですね。
でも、そうすると、Because I was sick.では、becauseは「接続の機能」を果たしていないじゃないかという矛盾に気づく生徒もいるでしょう。
しかし、becauseが「接続の機能」を失ってしまった訳ではありません。別の配慮が働いているのです。
A: Why were you absent from school yesterday?
B: I was absent from school yesterday because I was sick in bed.
から、「重複部分」である〈I was absent from school yesterdy〉を相手に要点が伝わりやすいよう配慮して、「省略」した結果です。
A「昨日学校休んでどうしたん?」
B「〈昨日学校休んだんは〉風邪ひいて寝ててん」
B: Because I was sick in bed.
中学でbecauseを学ぶ基本的フレーズです。
Why~?に対して、Because~.で理由を述べるのだなということが刷り込まれます。ただ、Becauseは理由を述べる枕詞のようなものだとの理解が主で、品詞について意識が及ぶことはまれでしょう。
しかしやがて、次のような文に出会って、
We stopped playing tennis because it bagan to rain.
「We stopped playing tennis」「+ because←it began to rain.」
becauseは「理由を表す」と共に、前後の「文を結びつける」働きがあるのだと理解します。つまり、ifやwhenと同じ「接続詞」なんですね。
でも、そうすると、Because I was sick.では、becauseは「接続の機能」を果たしていないじゃないかという矛盾に気づく生徒もいるでしょう。
しかし、becauseが「接続の機能」を失ってしまった訳ではありません。別の配慮が働いているのです。
A: Why were you absent from school yesterday?
B: I was absent from school yesterday because I was sick in bed.
から、「重複部分」である〈I was absent from school yesterdy〉を相手に要点が伝わりやすいよう配慮して、「省略」した結果です。
A「昨日学校休んでどうしたん?」
B「〈昨日学校休んだんは〉風邪ひいて寝ててん」
伊集院静に酔わされて
2025/4/2
昨日(4/1)、学校を始め多くの年度が新しくなりました。既に故人となられた作家が、サントリーウイスキーの広告文として、20年以上書き続けてこられた新社会人への贈る言葉の一節です。新しい出会いが素晴らしいものになりますように。
新社会人おめでとう。今日、君はどんな服装をして、どんな職場へ行ったのだろうか。たとえどんな仕事についても、君が汗を掻いてくれることを希望する。冷や汗だってかまわない。君は今、空っぽのグラスと同じなんだ。空の器と言ってもいい。どの器も今は大きさが一緒なのだ。学業優秀などというのは高が知れている。誰だってすぐに覚えられるほど社会の、世の中の、仕事というものは簡単じゃない。要領など覚えなくていい。小器用にこなそうとしなくていい。それよりももっと肝心なことがある。
それは仕事の心棒に触れることだ。たとえどんな仕事であれ、その仕事が存在する理由がある。資本主義というが、金を儲けることがすべてのものは、仕事なんかじゃない。仕事の心棒は、自分以外の誰かのためにあると、私は思う。その心棒に触れ、熱を感じることが大切だ。仕事の汗は、その情熱が出させる。心棒に、肝心に触れるには、いつもベストをつくして、自分が空っぽになってむかうことだ。
論理的思考をあきらめるな~corollary
2025/3/30
令和7年度大学入学共通テスト〈英語〉は、5年の時をかけ熟成され良質な問題に仕立てられた。それでも共通テストの基本的性質は変わらない。超長文の中で、情報の検索能力と適否判断能力が求められる。選択肢の中から、テクストに一番沿ったものがどれであるかを見極められればそれでよい。処理能力が問われ、思考は求められない。
おそらく、教育行政の要路に立つ人は、「要求をてきぱきこなす人材」を育成したいのだろう。「思考する」者は全体の2%もいればよい(それなら育まなくても自然発生に期待できる)。残りの98%は「思考せず、与えられた仕事で求められる成果を出しさえすればよい」がメタ・メッセージだ。
課されるのであれば、対応しなければならない。しょうがないから面従腹背を決め込もう。しかし、知性は思考を求める。仮面の裏側に「思考」を忍ばせよう。
「論理が要求する結論」のことを英語ではcorollaryという。思考を何重にも巡らして得た結論であるのなら、孤立を恐れず「これはコロラリーである」と言い切る勇気を持つこと。それが論理的に思考するということだ。
〈内田 樹の論を下敷きにしたつもりです〉
おそらく、教育行政の要路に立つ人は、「要求をてきぱきこなす人材」を育成したいのだろう。「思考する」者は全体の2%もいればよい(それなら育まなくても自然発生に期待できる)。残りの98%は「思考せず、与えられた仕事で求められる成果を出しさえすればよい」がメタ・メッセージだ。
課されるのであれば、対応しなければならない。しょうがないから面従腹背を決め込もう。しかし、知性は思考を求める。仮面の裏側に「思考」を忍ばせよう。
「論理が要求する結論」のことを英語ではcorollaryという。思考を何重にも巡らして得た結論であるのなら、孤立を恐れず「これはコロラリーである」と言い切る勇気を持つこと。それが論理的に思考するということだ。
〈内田 樹の論を下敷きにしたつもりです〉
トレーナー
2025/3/26
去年の夏は暑かったが、今年の冬は寒かった。麗美な四季の国は、今や長い夏と厳しい冬の二季化が顕著だ。寒い冬には高性能なインナーが欠かせないが、アウターにも温かいものを求めたい。かつてはチャンピオンプロダクツの厚手のトレーナーなどが秋冬のアスリートの定番アウターだった気がする。
trainerは本来、教える側の「教官」を指す言葉で、教わる側の「研修生」はtraineeと言う。ファストフードの店などでは、店員の名札にかわいく「trainee」と入っている場合がある。客が店員を育てなければならないのであって、カスタマー・ハラスメントなどをバラまく者は、店長が厳しく「出禁」に処さなければならない。
日本語のトレーナーは、sweat shirtというのが英語表現で、本来「トレーナー」では「スウェット・シャツ」の意味にはならない。日本語のトレーナーは、かのVANの創始者・石津謙介が作り出した和製英語である。パーカーも同様に石津氏の創出語で、英語ではフードのついた衣類を表す「フーディー」(hoodie)と呼ばれる。
チャンピオンプロダクツのトレーナーはいかにも「らしい」が、VANのトレーナーもかつてはアイビーファッションには無くてはならないものだった。
For the young and the young-at-heartが懐かしい。
trainerは本来、教える側の「教官」を指す言葉で、教わる側の「研修生」はtraineeと言う。ファストフードの店などでは、店員の名札にかわいく「trainee」と入っている場合がある。客が店員を育てなければならないのであって、カスタマー・ハラスメントなどをバラまく者は、店長が厳しく「出禁」に処さなければならない。
日本語のトレーナーは、sweat shirtというのが英語表現で、本来「トレーナー」では「スウェット・シャツ」の意味にはならない。日本語のトレーナーは、かのVANの創始者・石津謙介が作り出した和製英語である。パーカーも同様に石津氏の創出語で、英語ではフードのついた衣類を表す「フーディー」(hoodie)と呼ばれる。
チャンピオンプロダクツのトレーナーはいかにも「らしい」が、VANのトレーナーもかつてはアイビーファッションには無くてはならないものだった。
For the young and the young-at-heartが懐かしい。

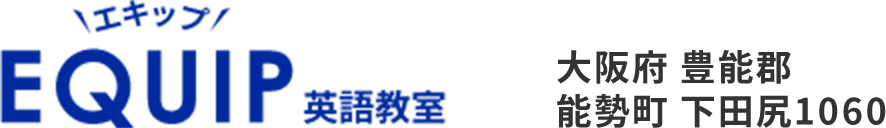


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
