塾長 ブログ
「~するように言う」は依頼/命令?
2025/3/9
「…に~するように言う」は、日本語では「依頼」の意味でも、「命令」の意味でも使用される表現ですが、英語では文意に応じて動詞を使い分けなければいけません。
〈依頼〉の場合、askを用いて、ask+人+to (V)の形で使います。
Please ask your friend to drive you to the station
では、命令の意とするためには動詞は何を使えばよいでしょう?
orderはもちろん「命令」の意ですが、[longman]によれば、
order: to tell someone that they must do something, using your official power or authority と「公的な力の行使である」と定義し、次の例文をあげています。
A policeman ordered him to stop.
ですので、〈「私→私」の指示・命令〉の意を表す時には、orderではなく、tellを使って、次のように表現します。
Please stop telling me what to do.
「私にあれこれ指図するのはやめてちょうだい」
ですから、tell+人+to (V)を「人に~するよう言う」とするのは少し曖昧で、askとの区別を明確にするために「人に~するよう命じる」の意味を与えた方がいいでしょう。
〈依頼〉の場合、askを用いて、ask+人+to (V)の形で使います。
Please ask your friend to drive you to the station
では、命令の意とするためには動詞は何を使えばよいでしょう?
orderはもちろん「命令」の意ですが、[longman]によれば、
order: to tell someone that they must do something, using your official power or authority と「公的な力の行使である」と定義し、次の例文をあげています。
A policeman ordered him to stop.
ですので、〈「私→私」の指示・命令〉の意を表す時には、orderではなく、tellを使って、次のように表現します。
Please stop telling me what to do.
「私にあれこれ指図するのはやめてちょうだい」
ですから、tell+人+to (V)を「人に~するよう言う」とするのは少し曖昧で、askとの区別を明確にするために「人に~するよう命じる」の意味を与えた方がいいでしょう。
comfort zone
2025/3/5
現代はインターネットの時代で、英語で書かれた評論や記事、さまざまなテクストに容易く接近可能になった。それに伴い、高校入試や大学入試に引用される英文も多様になり、逆に言えば使い捨てされるようになっている。かつてのように、一つの重要テクストが何年にも渡り繰り返し入試問題として使用されることは無くなった。
かつての頻出英文の一つに「comfort zone」を挙げることができるだろう。これは「Living in the U.S.A.」(Mrs. Lanier著)の〈distance and bodily contact〉からの借用だ。その最初のパラグラフを紹介しよう。
Did you know that all human beings have a comfort zone regarding the distance they stand from someone when they talk? The distance varies in interesting ways among people of different cultures.
現在、50歳台以上の世代であれば、学んだ記憶があるのではないだろうか。
かつての頻出英文の一つに「comfort zone」を挙げることができるだろう。これは「Living in the U.S.A.」(Mrs. Lanier著)の〈distance and bodily contact〉からの借用だ。その最初のパラグラフを紹介しよう。
Did you know that all human beings have a comfort zone regarding the distance they stand from someone when they talk? The distance varies in interesting ways among people of different cultures.
現在、50歳台以上の世代であれば、学んだ記憶があるのではないだろうか。
educationとは何か
2025/3/2
educationとは「教育」のことですが、日本語が表す「教育」の方が適用範囲が広いようです。
educationを[longman]で引くと、
the process of teaching and learning, usually at aschool, college, or university
と定義され、「学校教育」のことを指すのだということが分かります。「社員教育」などと日本語では「教育」を拡大しますが、会社がおこなう教育はeducationではありません。それはtrainingです。
[longman]ではtrainingを、
the process of teaching or being taught the skills for a particular job or activity
と説明し、特定の仕事に係る技術習得のことを表すのが分かります。
そして、education/training共に、「教える側」と「学ぶ側」双方に係る行為であることも分かります。
Department stores in Tokyo generally provide excellent service, and the staff are well-trained and courteous.
「東京のデパートは概してサービスが素晴らしい。社員はしっかりした教育を受けているし、とても礼儀正しい」(『よくばり英作文』)
educationを[longman]で引くと、
the process of teaching and learning, usually at aschool, college, or university
と定義され、「学校教育」のことを指すのだということが分かります。「社員教育」などと日本語では「教育」を拡大しますが、会社がおこなう教育はeducationではありません。それはtrainingです。
[longman]ではtrainingを、
the process of teaching or being taught the skills for a particular job or activity
と説明し、特定の仕事に係る技術習得のことを表すのが分かります。
そして、education/training共に、「教える側」と「学ぶ側」双方に係る行為であることも分かります。
Department stores in Tokyo generally provide excellent service, and the staff are well-trained and courteous.
「東京のデパートは概してサービスが素晴らしい。社員はしっかりした教育を受けているし、とても礼儀正しい」(『よくばり英作文』)
第3回英検結果からの学習アドバイス
2025/2/26
英検受験者向けのフィードバックです。英語力向上の参考に。
〈3級〉
①単語や熟語を使えるようにするために、例文と共に学習する。
②文法はその使い方のポイントを含んだ例文で覚える。
③一つ一つの単語を日本語に訳すのではなく、語順に沿って、意味のまとまりごとに理解する。
④英語の音やリズム、スピードに慣れるため、手本となる音声のすぐ後について英文を読む練習をする。
〈4級〉
①単語や熟語は、意味だけではなく、発音・綴り・使い方も同時に学習する。
②単語や熟語は、ノートやカードで整理し、繰り返し学習する。
③Who, What, Where, When, Why, Howを常に意識して読み、聞く。
④意味の分かった英文を繰り返し音読するのは、読解や聞き取る力を伸ばすことに繋がる。
各級で共通しているアドバイスに注目しましょう。意識の持ち方が、結果の良否に繋がります。
〈3級〉
①単語や熟語を使えるようにするために、例文と共に学習する。
②文法はその使い方のポイントを含んだ例文で覚える。
③一つ一つの単語を日本語に訳すのではなく、語順に沿って、意味のまとまりごとに理解する。
④英語の音やリズム、スピードに慣れるため、手本となる音声のすぐ後について英文を読む練習をする。
〈4級〉
①単語や熟語は、意味だけではなく、発音・綴り・使い方も同時に学習する。
②単語や熟語は、ノートやカードで整理し、繰り返し学習する。
③Who, What, Where, When, Why, Howを常に意識して読み、聞く。
④意味の分かった英文を繰り返し音読するのは、読解や聞き取る力を伸ばすことに繋がる。
各級で共通しているアドバイスに注目しましょう。意識の持ち方が、結果の良否に繋がります。
no longerをどこに置く
2025/2/23
「もはや~ない」を意味するno longer。通例、否定文で使われる「…を耐える」を意味するstandを使った次の文との組み合わせを考えます。
I can stand this hot weather. + 〈no longer〉
「もうこの暑さには耐えられない」
no longerをどこに置くのが適切でしょうか。
I can stand this hot weather.
△ △ △ △ △
① ② ③ ④ ⑤
おそらく、英語を学習している人なら、④と⑤の可能性はないと自然に考えられると思います。this hot weatherはひとまとまりの意味を作るchunk(語句の塊)になっていて、no longerが割って入る隙間がないのです。
では、①~③のどこが適当ですか。また、そう考える理由は?
ポイントはnoです。noはnotと同じく否定を表す語です。この場合、no longer「もはや~ない」はcan stand「我慢できる」を修飾する関係になるので、can standのどこにnotを置くかを考えれば、同じ位置にno longerを置けばよいことに気づけます。
I cannot stand this hot weather.
↓
I can no longer stand this hot weather.
I can stand this hot weather. + 〈no longer〉
「もうこの暑さには耐えられない」
no longerをどこに置くのが適切でしょうか。
I can stand this hot weather.
△ △ △ △ △
① ② ③ ④ ⑤
おそらく、英語を学習している人なら、④と⑤の可能性はないと自然に考えられると思います。this hot weatherはひとまとまりの意味を作るchunk(語句の塊)になっていて、no longerが割って入る隙間がないのです。
では、①~③のどこが適当ですか。また、そう考える理由は?
ポイントはnoです。noはnotと同じく否定を表す語です。この場合、no longer「もはや~ない」はcan stand「我慢できる」を修飾する関係になるので、can standのどこにnotを置くかを考えれば、同じ位置にno longerを置けばよいことに気づけます。
I cannot stand this hot weather.
↓
I can no longer stand this hot weather.

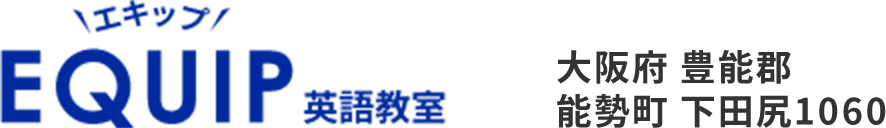


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
