塾長 ブログ
be動詞の2つの意味
2024/9/25
英語学習初期に習うbe動詞。
①「=」で表される連結動詞としての働きが最初に出てきます。
I=a teacher.→I am a teacher.
You=a student.→You are a student.
She=Ms. White.→She is Ms. White.
最初の刷り込みが大きな印象を残すためか、be動詞は「=」の働きと理解して記憶される場合が多いようです。しかし、be動詞は、
②「存在する」の意味も持ち合わせます。
He is at the library.
「彼=図書館に」でも最低限の意味理解は可能ですが、「彼は図書館に『存在する』」→「彼は図書館にいる」と理解しておく方が、将来の学習の広がりに対応しやすくなります。
How long will you be in New York?
これも「存在する」→「滞在する」のルートを辿るべきでしょう。
①「=」で表される連結動詞としての働きが最初に出てきます。
I=a teacher.→I am a teacher.
You=a student.→You are a student.
She=Ms. White.→She is Ms. White.
最初の刷り込みが大きな印象を残すためか、be動詞は「=」の働きと理解して記憶される場合が多いようです。しかし、be動詞は、
②「存在する」の意味も持ち合わせます。
He is at the library.
「彼=図書館に」でも最低限の意味理解は可能ですが、「彼は図書館に『存在する』」→「彼は図書館にいる」と理解しておく方が、将来の学習の広がりに対応しやすくなります。
How long will you be in New York?
これも「存在する」→「滞在する」のルートを辿るべきでしょう。
リスニング力を上げる
2024/9/22
英検でも、共通テスト〈英語〉でも、リスニング試験が実施され評価されます。リスニング力を上げるのに多聴は有効ですが、単に聞き流していては時間の無駄となるでしょう。よく言われることですが、発音できない語は聞き取ることができません。自分の発音をネイティブに近づけていくことがリスニング学習の核心です。
リスニングと同時並行的に、自分の発音を「ネイティブの音とスピード・リズム」に近づけていくアウトプット(発話練習)の取り組みが必要です。聞いているだけでは身につくものはほとんどなく、自分の音声をリスニング音源にかぶせて模倣することが鍵になります。学習者が音のみを手掛かりにリスニングを追いかけることは難しいので、スクリプト(原稿)のある教材を選んでください。
音を中心とする学習は、長文読解や文法学習をする際に使用する脳の領域とは別の場所を使うことになるようです。上手く活用すれば、疲労感を感じずに効果的な学習をすることができると思います。すき間学習にも良いかもしれません。
スクリプトを見ながら、ネイティブスピードでリスニングすることが「自分の普通」になれば、長文読解のリーディングスピードも飛躍的に上がると思います。共通テストの長文化に対する対策としても効果が高いものだと考えます。
リスニングと同時並行的に、自分の発音を「ネイティブの音とスピード・リズム」に近づけていくアウトプット(発話練習)の取り組みが必要です。聞いているだけでは身につくものはほとんどなく、自分の音声をリスニング音源にかぶせて模倣することが鍵になります。学習者が音のみを手掛かりにリスニングを追いかけることは難しいので、スクリプト(原稿)のある教材を選んでください。
音を中心とする学習は、長文読解や文法学習をする際に使用する脳の領域とは別の場所を使うことになるようです。上手く活用すれば、疲労感を感じずに効果的な学習をすることができると思います。すき間学習にも良いかもしれません。
スクリプトを見ながら、ネイティブスピードでリスニングすることが「自分の普通」になれば、長文読解のリーディングスピードも飛躍的に上がると思います。共通テストの長文化に対する対策としても効果が高いものだと考えます。
メジャーリーグ、朝飯前トレーニング
2024/9/18
日本人は勤勉だとよく言われますが、外国の方にも勤勉な方は多いです。眉間にしわを寄せて必死に頑張るのが日本人スタイルなら、楽しみながら必死に頑張るのがアメリカ人のスタイルなのかもしれません。
全体をゆるく見ていると、ステレオタイプなものの見方を脱するのは難しいけれど、個々の人をよく見てみると当然ながら人によって行動も語る言葉も異なります。
昔、アメリカのメジャーリーグに挑戦したある日本人選手が「アメリカ人は全然練習しない。朝食後、早めに球場に行ってトレーニングしているのは僕くらい」のような発言をするのを聞いたことがあります。彼の習慣的行動様式に基づいて観察するとそう思えたのでしょうね。
でも、多くのアスリートは朝食前に運動します。その方が食事による血糖値上昇の影響を受けずに、トレーニングできる利点もあります。おそらく、アメリカ人選手が早起きして、「朝飯前トレーニング」をしてから、朝食をゆっくり摂る習慣を知らず、朝ご飯をかき込んで、「何だよ。奴ら、ゆっくり球場に出てきやがって」くらいに思っていたのでしょうね。さて、一日のスタートで出遅れた日本人選手のその後の活躍ぶりは…。
全体をゆるく見ていると、ステレオタイプなものの見方を脱するのは難しいけれど、個々の人をよく見てみると当然ながら人によって行動も語る言葉も異なります。
昔、アメリカのメジャーリーグに挑戦したある日本人選手が「アメリカ人は全然練習しない。朝食後、早めに球場に行ってトレーニングしているのは僕くらい」のような発言をするのを聞いたことがあります。彼の習慣的行動様式に基づいて観察するとそう思えたのでしょうね。
でも、多くのアスリートは朝食前に運動します。その方が食事による血糖値上昇の影響を受けずに、トレーニングできる利点もあります。おそらく、アメリカ人選手が早起きして、「朝飯前トレーニング」をしてから、朝食をゆっくり摂る習慣を知らず、朝ご飯をかき込んで、「何だよ。奴ら、ゆっくり球場に出てきやがって」くらいに思っていたのでしょうね。さて、一日のスタートで出遅れた日本人選手のその後の活躍ぶりは…。
make 意味の広がり
2024/9/15
makeは基本動詞で、英語学習の初期に「作る」の意味で習います。
I make salad every morning. [×cook salad]
cookは「加熱」料理なので、サラダと馴染みません。
さらに、目的語を2つとる、
She made Bill a new suit.
make+O1+O2「O1にC2を作ってやる」の表現を経て、
make+O+C「OをCの状態にする」に出会います。
〈Cが名詞〉
The movie made her a star. [her→a star]
〈Cが形容詞〉
The news made them happy. [them→happy]
[使役動詞]make+O+(V)も、[O→C]の関係は上と同じです。
My mother made me clean my room. [me→clean]
〈Cが過去分詞〉を最後習うのはOとCの関係が異なるため。
I couldn't make mysellf understood in English. [O←C]
「私は自分のことを英語で理解してもらうことができなかった」
→「私の英語は通じなかった」
I make salad every morning. [×cook salad]
cookは「加熱」料理なので、サラダと馴染みません。
さらに、目的語を2つとる、
She made Bill a new suit.
make+O1+O2「O1にC2を作ってやる」の表現を経て、
make+O+C「OをCの状態にする」に出会います。
〈Cが名詞〉
The movie made her a star. [her→a star]
〈Cが形容詞〉
The news made them happy. [them→happy]
[使役動詞]make+O+(V)も、[O→C]の関係は上と同じです。
My mother made me clean my room. [me→clean]
〈Cが過去分詞〉を最後習うのはOとCの関係が異なるため。
I couldn't make mysellf understood in English. [O←C]
「私は自分のことを英語で理解してもらうことができなかった」
→「私の英語は通じなかった」
駿台教育探求セミナーより
2024/9/11
9/8(日)、駿台上本町校でおこなわれた竹岡 広信先生の講座を受講した。50分の講義が午前に3コマ、午後に3コマあり、質疑応答が終了したのは17時を回っていたが、充実した時間は飛ぶように過ぎた。現在、エキップ英語教室以外に、ある高校で2年生を週3回教えているので、彼らの英語力強化に役立つよう、セミナーで学んだ事項を授業に織り込んでいこうと思う。
さて、竹岡先生の講座はいつも有意義な情報をもたらしてくれるが、今回は竹岡先生が授業で重視されている英文法を共有したい。
1. 関係代名詞、時制、比較、助動詞は中学レベルからやり直し
2. SVOC(allow O to (V)など)
3. must have (V)p.p. / S seem to have (V)p.p.などのhave (V)p.p.
4. 強調構文(分裂文)
5. 分詞構文の基本
6, 否定的副詞+倒置(疑問文の語順)
さて、竹岡先生の講座はいつも有意義な情報をもたらしてくれるが、今回は竹岡先生が授業で重視されている英文法を共有したい。
1. 関係代名詞、時制、比較、助動詞は中学レベルからやり直し
2. SVOC(allow O to (V)など)
3. must have (V)p.p. / S seem to have (V)p.p.などのhave (V)p.p.
4. 強調構文(分裂文)
5. 分詞構文の基本
6, 否定的副詞+倒置(疑問文の語順)

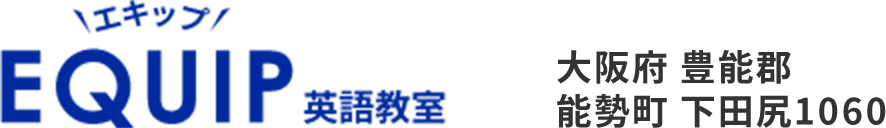


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
