塾長 ブログ
納屋、その後、エキップ英語教室③
2024/2/6
教室は、エプソン社製プロジェクタによるICTシステムを備えます。
長文読解なのに、「板書するのに時間がかかるから、3回の授業に分けて」というようなことにはなりません。電子黒板機能のおかげで、1回の授業で一つの長文をスッキリ解説し終えることができます。
内臓スピーカーから音声を流すことができるので、リスニングを並行させることにより、理想的なリーディングスピードを明示することも可能です。
長文読解なのに、「板書するのに時間がかかるから、3回の授業に分けて」というようなことにはなりません。電子黒板機能のおかげで、1回の授業で一つの長文をスッキリ解説し終えることができます。
内臓スピーカーから音声を流すことができるので、リスニングを並行させることにより、理想的なリーディングスピードを明示することも可能です。
納屋、その後、エキップ英語教室②
2024/2/4
エキップ英語教室の前身は納屋でした。
教室にリモデルする(この意味でリフォームを使うのは和製英語です。reformは教育「改革」などの場合に用います)に当たり、特に気を配ったのは、「耐震性能の向上」と「冬の寒さ対策」です。
教室は学習の場ですが、その基盤となるのは「安全・安心」な施設です。
教室にリモデルする(この意味でリフォームを使うのは和製英語です。reformは教育「改革」などの場合に用います)に当たり、特に気を配ったのは、「耐震性能の向上」と「冬の寒さ対策」です。
教室は学習の場ですが、その基盤となるのは「安全・安心」な施設です。
納屋、その後、エキップ英語教室①
2024/2/2
今日は、エキップ英語教室への行き方を案内します。
徒歩、自転車、自家用車での送迎。最適な方法を選択してください。
先ずは、府道106号線と府道4号線が交差する「田尻」交差点まで来てください。
そこから、ガソリン・スタンドの反対側、北東方向を眺めます。↓
徒歩、自転車、自家用車での送迎。最適な方法を選択してください。
先ずは、府道106号線と府道4号線が交差する「田尻」交差点まで来てください。
そこから、ガソリン・スタンドの反対側、北東方向を眺めます。↓
錆びた水色の貨車と白のガレージが見えるでしょうか。
その間に白い欄干が見えますか?そこに最寄りの藤木橋があります。
2/2現在、この橋はGoogleマップでは表示されていません。(修正申請済)
白色のガレージを目指して進んでください。↓
その間に白い欄干が見えますか?そこに最寄りの藤木橋があります。
2/2現在、この橋はGoogleマップでは表示されていません。(修正申請済)
白色のガレージを目指して進んでください。↓
藤木橋の上からエキップ英語教室を見ると、こんな風です。
白色のガレージの前に軽自動車6台分の駐車場があります。
車利用の方は、ここに駐車して、そのまま坂を歩いて上がってください。
徒歩・自転車の人はそのまま上までお進みください。↓
白色のガレージの前に軽自動車6台分の駐車場があります。
車利用の方は、ここに駐車して、そのまま坂を歩いて上がってください。
徒歩・自転車の人はそのまま上までお進みください。↓
学習をスポーツに例える難しさ②
2024/1/31
生徒の頭の中で、今何が起こっているのか。ニューロンは発火しているか否か。果たして、シナプスは接続しているのか否か。本人が「やってますよー」と言っても、目標に対して今どの程度まで接近しているか、授業中に生徒の頭の中を覗いてみることは出来ません。
ではどうやって現状を把握すればよいでしょう。
エキップ英語教室では、出力(課題の成果や小テスト)を確認・評価することで、遡及的に、その出力に至った生徒の頭の中での処理(その時の現状=どんなふうに勉強していたか)の適否を判定し、改善に向けて適切に助言します。
生徒の頭の中での活動が、ブラックボックス的な把握・操作できないものとはならないように、結果が全ての立場で評価することを大切にしようと思います。
家庭での課題学習は自分の勉強に繋がるように工夫が必要ですし、教室で実施する小テストは「いつも満点」でなければいけません。それが普通。7割出来たというのは、ほぼ出来てないと同義と心得てください。
ではどうやって現状を把握すればよいでしょう。
エキップ英語教室では、出力(課題の成果や小テスト)を確認・評価することで、遡及的に、その出力に至った生徒の頭の中での処理(その時の現状=どんなふうに勉強していたか)の適否を判定し、改善に向けて適切に助言します。
生徒の頭の中での活動が、ブラックボックス的な把握・操作できないものとはならないように、結果が全ての立場で評価することを大切にしようと思います。
家庭での課題学習は自分の勉強に繋がるように工夫が必要ですし、教室で実施する小テストは「いつも満点」でなければいけません。それが普通。7割出来たというのは、ほぼ出来てないと同義と心得てください。
学習をスポーツに例える難しさ①
2024/1/29
成し遂げようとする目的を定めて、それを達成するために目標を持って取り組むという点で、学習とスポーツは良く似ています。
〇〇大学に合格するという目的を決めて、じゃあ英語は高3になるまでに英検2級を取得するという目標を持つ。陸上競技でインターハイに出場するという目的を決めて、じゃあ今月はこのタイムを出すという目標を決める。学習とスポーツは本当にそっくりです。しかし、視覚による現状の捉えやすさという点で、2つは大きく異なります。
スポーツの場合、ビデオで自分の動きを撮れば、目標に対して自分が今どの程度まで接近しているか客観的に現状把握が出来る場合も多いでしょう。一方、学習の今を視覚化するのは困難です。
生徒の頭の中で、今何が起こっているのか。ニューロンは発火しているか否か。果たして、シナプスは接続しているのか否か。本人が「やってますよー」と言っても、目標に対して今どの程度まで接近しているか、授業中に生徒の頭の中を覗いてみることは出来ません。
〈to be continued〉
〇〇大学に合格するという目的を決めて、じゃあ英語は高3になるまでに英検2級を取得するという目標を持つ。陸上競技でインターハイに出場するという目的を決めて、じゃあ今月はこのタイムを出すという目標を決める。学習とスポーツは本当にそっくりです。しかし、視覚による現状の捉えやすさという点で、2つは大きく異なります。
スポーツの場合、ビデオで自分の動きを撮れば、目標に対して自分が今どの程度まで接近しているか客観的に現状把握が出来る場合も多いでしょう。一方、学習の今を視覚化するのは困難です。
生徒の頭の中で、今何が起こっているのか。ニューロンは発火しているか否か。果たして、シナプスは接続しているのか否か。本人が「やってますよー」と言っても、目標に対して今どの程度まで接近しているか、授業中に生徒の頭の中を覗いてみることは出来ません。
〈to be continued〉

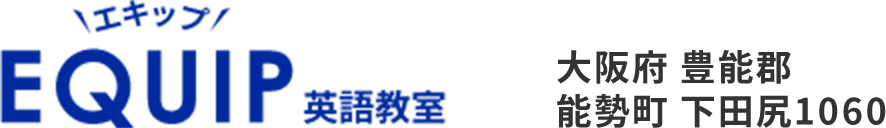


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
