塾長 ブログ
時制の一致の例外
2026/2/8
時制の一致というのは、
Mike tells me that he plays tennis on weekends.
という文の、主節の動詞がtoldと過去形になった場合には、従属節の中の動詞もそれに合わせてplayedと時制を合わせなければならないという英語規則のことです。
→Mike told me that he played tennis on weekends.
しかし、従属節の動詞が表す時制が「現在でも変わらない内容」である場合などでは、この時制の一致が適用されないこともあります。R8年度共通テスト第1問のtext messagesの中に次のような文がありました。
Let's not forget to talk with our instructor before we make the final decision about what costumes to buy. She said she's available before rehearsal tomorrow.
コーチは「明日のリハーサル前なら時間の都合をつけれらる」と言っていたが、それがその時点だけではなく、今もなお有効であることを示しています。
Mike tells me that he plays tennis on weekends.
という文の、主節の動詞がtoldと過去形になった場合には、従属節の中の動詞もそれに合わせてplayedと時制を合わせなければならないという英語規則のことです。
→Mike told me that he played tennis on weekends.
しかし、従属節の動詞が表す時制が「現在でも変わらない内容」である場合などでは、この時制の一致が適用されないこともあります。R8年度共通テスト第1問のtext messagesの中に次のような文がありました。
Let's not forget to talk with our instructor before we make the final decision about what costumes to buy. She said she's available before rehearsal tomorrow.
コーチは「明日のリハーサル前なら時間の都合をつけれらる」と言っていたが、それがその時点だけではなく、今もなお有効であることを示しています。
受験に向けた0学期
2026/2/4
中2生や高2生が新学年を迎えるのは4月ですが、大学受験では年内に入学試験が実施され、その受験方法を志向する生徒も多くいます。11月には年内学力入試があるとすると、今からの準備期間は10か月しかないということになります。
高2生はこの時期、課外活動の中心を担う生徒たちでもあるので、本格的な受験勉強とはいかないまでも、受験に向けた学習の核となる部分についてはおよそ把握できている状態にしておきたいものです。「受験勉強はクラブを引退してから」と考えていると、年内入試に向けてはほんの3カ月ほどしか時間がないということになりかねません。
年明けから始まる3学期を、高3の0学期と呼称することもこのためです。二兎を追いかけることは簡単ではありませんが、まず「基礎の基礎」を1月~3月までの期間に固め、何よりも学習習慣を確立しておくことが、高3段階までの今の時期に求められることでしょう。
高2生はこの時期、課外活動の中心を担う生徒たちでもあるので、本格的な受験勉強とはいかないまでも、受験に向けた学習の核となる部分についてはおよそ把握できている状態にしておきたいものです。「受験勉強はクラブを引退してから」と考えていると、年内入試に向けてはほんの3カ月ほどしか時間がないということになりかねません。
年明けから始まる3学期を、高3の0学期と呼称することもこのためです。二兎を追いかけることは簡単ではありませんが、まず「基礎の基礎」を1月~3月までの期間に固め、何よりも学習習慣を確立しておくことが、高3段階までの今の時期に求められることでしょう。
by the time S+V
2026/2/1
till/unitlは名詞の前に付ける前置詞としても、S+Vの文構造の前に置く接続詞としても使われ、[継続の期限:…までずっと]を表す。ポイントは「…まで」ではなく、「…までずっと」まできっちり記憶すること。
一方byは前置詞で、[完了の期限:…までには]の意味。こちらも「…まで」だと、till/untilとの区別がつかなくなってしまうので、「…までには」と記憶しておかなければ実際には使えない。
さて、問題は、では「~までには」の後ろにS+Vの文構造を続け、「あなたが帰って来るまでには」としたい時にはどうすればいいかということだろう。そんな時はby the time S+Vを用いて、
I'll have finished it by the time you get back.
とすればいい。by the timeは「前置詞+名詞」で、その後ろに関係副詞whenが省略されていると考えれば、文法的にも無理なく理解できるだろう。ただし、by the time when you get backとは通例用いられないので、by the time+SVで記憶しよう。
一方byは前置詞で、[完了の期限:…までには]の意味。こちらも「…まで」だと、till/untilとの区別がつかなくなってしまうので、「…までには」と記憶しておかなければ実際には使えない。
さて、問題は、では「~までには」の後ろにS+Vの文構造を続け、「あなたが帰って来るまでには」としたい時にはどうすればいいかということだろう。そんな時はby the time S+Vを用いて、
I'll have finished it by the time you get back.
とすればいい。by the timeは「前置詞+名詞」で、その後ろに関係副詞whenが省略されていると考えれば、文法的にも無理なく理解できるだろう。ただし、by the time when you get backとは通例用いられないので、by the time+SVで記憶しよう。
仮想ライバルを作ろう
2026/1/28
どうも思うように学習に身が入らない。勉強し始めてはみるものの、長続きしない。これらは誰にでも起こりそうなことですね。学力育成には「昨日の自分を越えて」いくことが求められるのですが、相手が自分となると「自分が自分の正体を掴めない」がゆえに、いろいろな邪念や打算の誘惑に抗するのが難しくなったりするものです。
そういう時に有効なのが、同じクラスや学年に「仮想ライバル」生徒を設定して、その人には負けないように自分を叱咤激励するという方法です。出来れば自分より少し学力が高いと思われる生徒を仮想ライバルに設定するのがよいでしょう。前回の定期考査の点数差なんかが分かれば、学習意欲の維持により有効かもしれません。
科目が英語なら、英検級の取得を目標にするのも方法です。目標とする英検級を設定し、受験予定日に対し学習を重ねていく。結果は級の取得という形で現れるかもしれませんし、取得に至らなくても一次試験の突破とか、受験で得られるCSEスコアの伸びで自分の英語力の伸長を確かめることも可能だからです。
そういう時に有効なのが、同じクラスや学年に「仮想ライバル」生徒を設定して、その人には負けないように自分を叱咤激励するという方法です。出来れば自分より少し学力が高いと思われる生徒を仮想ライバルに設定するのがよいでしょう。前回の定期考査の点数差なんかが分かれば、学習意欲の維持により有効かもしれません。
科目が英語なら、英検級の取得を目標にするのも方法です。目標とする英検級を設定し、受験予定日に対し学習を重ねていく。結果は級の取得という形で現れるかもしれませんし、取得に至らなくても一次試験の突破とか、受験で得られるCSEスコアの伸びで自分の英語力の伸長を確かめることも可能だからです。
完了形が表すことは
2026/1/25
中学で英語を学習すると、時制として「現在」→「過去」→「未来」を表す表現を習います。そして「現在完了」。「完了」というのは、その基準となる時制の過去サイドを表す表現なので、現在完了であれば、現在の過去サイドを表す表現ということになります。
I lost the key.「鍵を失くしました」
が伝えるのは「過去のある時点で、鍵を紛失した」という事実のみです。その鍵がその後見つかったのか、あるいは失ったままなのかについては何も言及していません。
ですが、ここで現在完了を使うと、「鍵を失くして→今もまだ失くしたままだ」という〈現在の過去サイド〉全般を表現できるのです。
I have lost the key.「鍵を失ってしまった(今もまだ失ったままだ)」
現在完了は、日本語表現にはない時間把握の概念なので、最初とまどうかもしれませんが、「『完了』は基準となる時制の過去サイドを表す」と覚えておけば、過去完了や未来完了。それから不定詞や動名詞、分詞の「完了」表現などすべて同じ考え方で理解できるようになります。
I lost the key.「鍵を失くしました」
が伝えるのは「過去のある時点で、鍵を紛失した」という事実のみです。その鍵がその後見つかったのか、あるいは失ったままなのかについては何も言及していません。
ですが、ここで現在完了を使うと、「鍵を失くして→今もまだ失くしたままだ」という〈現在の過去サイド〉全般を表現できるのです。
I have lost the key.「鍵を失ってしまった(今もまだ失ったままだ)」
現在完了は、日本語表現にはない時間把握の概念なので、最初とまどうかもしれませんが、「『完了』は基準となる時制の過去サイドを表す」と覚えておけば、過去完了や未来完了。それから不定詞や動名詞、分詞の「完了」表現などすべて同じ考え方で理解できるようになります。

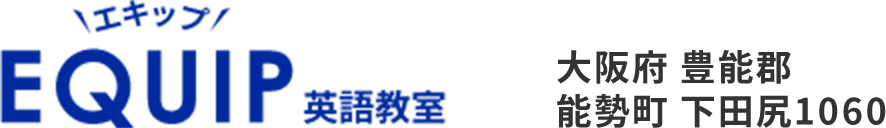


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
