塾長 ブログ
「『~した』は過去形で表す」は本当か
2026/1/4
日本語では「~した」と表現するものを、英語で表現しようとする場合には、「それが『現在』とつながりがあるか」を考える必要があります。
I lost the key yesterday.
なら、昨日「鍵を失くした」ことは分かりますが、その鍵が今どうなっているかはこの文からだけでは不明です。
I have lost the key.
と現在完了形で表現すれば、「鍵を失くしたということが、現在もまだ続いている」=「鍵がまだ見つかっていない」という意味になります。
「過去」と「現在」をつなぐ表現が「現在完了形」なのです。
だから、現在完了形と「過去を明示する語」を一緒に使うことはできません。
×I have lost the key yesterday.
I lost the key yesterday.
なら、昨日「鍵を失くした」ことは分かりますが、その鍵が今どうなっているかはこの文からだけでは不明です。
I have lost the key.
と現在完了形で表現すれば、「鍵を失くしたということが、現在もまだ続いている」=「鍵がまだ見つかっていない」という意味になります。
「過去」と「現在」をつなぐ表現が「現在完了形」なのです。
だから、現在完了形と「過去を明示する語」を一緒に使うことはできません。
×I have lost the key yesterday.
晦日と大晦日~2学期制・3学期制
2025/12/31
晦日(みそか)とは「その月の末日」のこと。その晦日のうちで一年最後の晦日となる日を大晦日と言います。今日はその大晦日。
大晦日にこの一年を振り返るというのは、日本人の心情と非常にうまく重なって、多くの人に自然に受け入れられるものでしょう。
そして、大晦日の翌日はもちろん元日「年の始めの日」。新しく始まる一年の平安を祈りに初詣に出かけるというのも、多くの人にとってしっくりくる行事でしょう。
年が明けて学校が再開されると3学期という場合が多いのですが、最近は2学期制を取り入れる自治体などもあり、その場合は2学期の後半途中から学校が再開されることになります。
2学期制のメリットは、学習日数をより多く確保することでしょうが、その学習定着を測る定期考査は回数が少なくなって、試験範囲は拡大します。一長一短ある訳ですが、「学びの質が上がり、学力がしっかり形成されたか」でもって、2学期制・3学期制の良否が判断される必要があるでしょう。
考査の負担感が少なく、春休み・夏休み・冬休みという社会の流れとうまく適合する3学期制が、生徒にも・教員にも・そして保護者にも、一番無理なくしっくり馴染む最適制度ではないでしょうか。
大晦日にこの一年を振り返るというのは、日本人の心情と非常にうまく重なって、多くの人に自然に受け入れられるものでしょう。
そして、大晦日の翌日はもちろん元日「年の始めの日」。新しく始まる一年の平安を祈りに初詣に出かけるというのも、多くの人にとってしっくりくる行事でしょう。
年が明けて学校が再開されると3学期という場合が多いのですが、最近は2学期制を取り入れる自治体などもあり、その場合は2学期の後半途中から学校が再開されることになります。
2学期制のメリットは、学習日数をより多く確保することでしょうが、その学習定着を測る定期考査は回数が少なくなって、試験範囲は拡大します。一長一短ある訳ですが、「学びの質が上がり、学力がしっかり形成されたか」でもって、2学期制・3学期制の良否が判断される必要があるでしょう。
考査の負担感が少なく、春休み・夏休み・冬休みという社会の流れとうまく適合する3学期制が、生徒にも・教員にも・そして保護者にも、一番無理なくしっくり馴染む最適制度ではないでしょうか。
「~したら」をどう表すか
2025/12/28
「~したらは、if節を用いて表す」確かに高校受験までは、概ねそれが答えとなるように想定されて作問されているので問題は生じにくいでしょう。
でもいつも「~したらをif節で表す」訳ではないのです。
例えば、「明日晴れたら~」というのは、確実にそうなる訳ではないので、
If it is[×will be] sunny tomorrow, we will go on a picnic.
とifを用いて表現しますが、これが「家に着いたら~」ならば、帰宅するのはまず間違いないことでしょうから、
When I get[×will get] home, I will call Tom and tell him that.
とwhenを用いて表現します。
時・条件を表す副詞節は、昔むかしは仮定法現在が適用され、
If it be sunny tomorrow, ~.
と表現されていましたが、「it be」なんておかしくね?と考える人が増え、今では動詞の現在形が使われるようになっています。
でもいつも「~したらをif節で表す」訳ではないのです。
例えば、「明日晴れたら~」というのは、確実にそうなる訳ではないので、
If it is[×will be] sunny tomorrow, we will go on a picnic.
とifを用いて表現しますが、これが「家に着いたら~」ならば、帰宅するのはまず間違いないことでしょうから、
When I get[×will get] home, I will call Tom and tell him that.
とwhenを用いて表現します。
時・条件を表す副詞節は、昔むかしは仮定法現在が適用され、
If it be sunny tomorrow, ~.
と表現されていましたが、「it be」なんておかしくね?と考える人が増え、今では動詞の現在形が使われるようになっています。
自己評価と外部評価
2025/12/24
自分のことは自分が一番よく分かっている、場合もある。
自分の現状課題について自分は常に把握している、場合もあるだろう。ただ、気をつけなければならないのは、そう判断しているのが一番信頼できる自分自身であったとしても、たった一人の意見や考えに違いはないことだ。
自分のことをとやかく言うのが同じ一人の相手であるならば、「1対1」の価値対決だから、自分が最も信頼を寄せる自分自身の導き出す意見に従うのもいいだろう。
だが、周囲の人たちの自分に対する評価が、自分自身による自己評価と異なる点があれば、これは「多対1」の図式だから、よくよく考えてみる必要があるのではないだろうか。多くの眼による自分の評価の方が、より客観的である可能性は相当程度高いのだから。
自分の現状課題について自分は常に把握している、場合もあるだろう。ただ、気をつけなければならないのは、そう判断しているのが一番信頼できる自分自身であったとしても、たった一人の意見や考えに違いはないことだ。
自分のことをとやかく言うのが同じ一人の相手であるならば、「1対1」の価値対決だから、自分が最も信頼を寄せる自分自身の導き出す意見に従うのもいいだろう。
だが、周囲の人たちの自分に対する評価が、自分自身による自己評価と異なる点があれば、これは「多対1」の図式だから、よくよく考えてみる必要があるのではないだろうか。多くの眼による自分の評価の方が、より客観的である可能性は相当程度高いのだから。
「~している」は常に進行形か
2025/12/21
Todd is cleaning his room now.
「トッドは今、自分の部屋を掃除している」
be+(V)ingで進行形を表します。(V)ingになるのは「動作動詞」なので
×I am knowing the news.
などとは表現できないことは多くの人が知っています。
では、「トッドは自分の部屋は自分で掃除している」はどうでしょう。この日本語は「普段から彼はそうだ」という「習慣」について言及しています。
「トッドは自分の部屋は自分で掃除する」ということなので、これは現在形で表現することになります。
Todd cleans his room.
日本語に惑わされずに、「現在進行中の動作(=現在進行形)」なのか「習慣的行動(=現在形)」なのかを把握する必要があります。
「トッドは今、自分の部屋を掃除している」
be+(V)ingで進行形を表します。(V)ingになるのは「動作動詞」なので
×I am knowing the news.
などとは表現できないことは多くの人が知っています。
では、「トッドは自分の部屋は自分で掃除している」はどうでしょう。この日本語は「普段から彼はそうだ」という「習慣」について言及しています。
「トッドは自分の部屋は自分で掃除する」ということなので、これは現在形で表現することになります。
Todd cleans his room.
日本語に惑わされずに、「現在進行中の動作(=現在進行形)」なのか「習慣的行動(=現在形)」なのかを把握する必要があります。

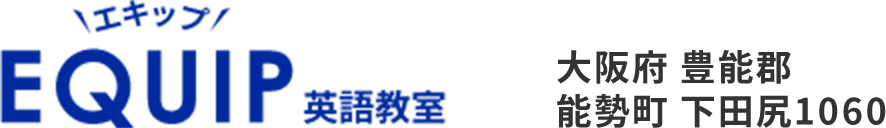


 FAQs
FAQs
 お問い合わせ
お問い合わせ
